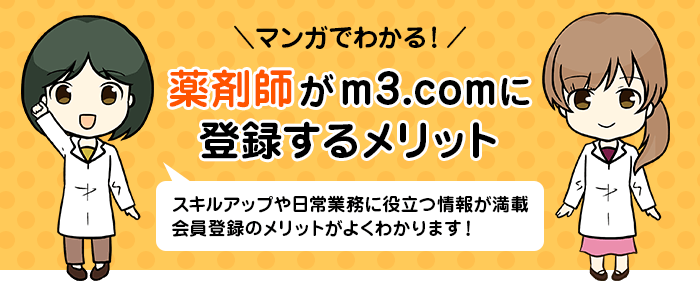特集
日々変化する医療や医薬に関する注目すべきトピックや情報にフォーカスしました。
-
特集
大腸がん発見による内視鏡の役割とは
厚生労働省の人口動態統計によれば、日本の大腸がん死亡数は増加し続けおり、その対策が急がれています。そんな大腸がんの早期診断・早期治療に有用なのが大腸内視鏡です。

-
特集
現代人が陥りがちな不眠症の誤解
私たちの体には、夜になると自然に眠たくなる体内時計のしくみが備わっています。それにもかかわらずなぜ不眠症になってしまうのでしょうか?

-
特集
超高齢社会で訪れる認知症との共生
認知症になってもその人らしく生きるためにはどうしたらよいのでしょうか?さらに家族や社会は認知症の人とどう向き合い、どう接したらよいのでしょう?

-
特集
2018年度調剤報酬・調剤報酬改定のポイント 病院薬剤師編
2018年度診療報酬・調剤報酬改定が4月1日よりスタートしました。病院薬剤師にとってどのような影響があるのか、今回の改定結果を活かすために知っておくべきポイントを、現場をよく知る専門家に解説していただきました。

-
特集
2018年度調剤報酬・調剤報酬改定のポイント 薬局薬剤師編
2018年度診療報酬・調剤報酬改定のポイント 薬局薬剤師編 2018年度診療報酬・調剤報酬改定が4月1日よりスタートしました。薬局薬剤師にとってどのような影響があるのか、今回の改定結果を活かすために知っておくべきポイントを、現場をよく知る専門家に解説していただきました。

-
特集
「薬が飲めない」摂食嚥下障害とは?
私たちは普段、口腔内や咽頭・喉頭の働きを意識しながら飲食することはほとんどありません。毎日当たり前に行っている、食べ物を見て、それを口に運び、咀嚼し、嚥下する一連の動きは実はとても複雑なのです。その過程を細かく見ていきましょう。

-
特集
アナフィラキシーの病態と対処法とは?
食物や薬剤、昆虫毒などが原因で起こる全身性のアレルギー症状を、アナフィラキシーといいます。アナフィラキシーは、アレルギー専門医に限らずすべての医療従事者が遭遇する可能性がある病態です。発症の原因やそのメカニズム、対処法について解説します。

-
特集
サルコペニア予防に適切な「スロートレーニング」とは? 第1部
高齢期に運動器などの機能低下によってADL、QOLが損なわれる病態として、近年、サルコペニアが注目されています。今回は、スポーツ科学の観点から、サルコペニアの予防について解説していただきます。

-
特集
超高齢化社会で注目される「サルコペニア」とは? 第2部
サルコペニアは1989年にアメリカで提唱された比較的新しい疾患概念です。診断基準については国際的にも国内的にも統一基準が確立されておらず、その対策が急がれています。今回は、サルコペニアについて解説していただきました。

-
特集
現代においてなぜうつ病は増え続けるのか?
社会全体に今までにないストレスが蔓延し、「コロナうつ」といった言葉も出てきましたが、 コロナ以前から、うつ病患者数は増加の一途を辿っています。うつ病はなぜ増え続けるのか?今回は、うつ病の病態や治療について解説いたします。

-
特集
2型糖尿病における治療戦略とは?
2 型糖尿病の患者数は、食生活の欧米化や人口の高齢化などによって増加しています。進行が緩徐で、発症しても気付きにくいのも特徴のひとつ。2 型糖尿病の治療戦略とは?

-
特集
アレルギー性鼻炎の診療に薬剤師のサポートが必要な理由
アレルギー性鼻炎は致死的な疾患ではありません が、生活の質(QOL)に影響し、いったん発症すると 自然治癒しにくく罹病期間が長いことから、適切な治療を行って症状をコントロールしていくことが必要になります。

-
特集
漢方の基礎と臨床 漢方の基本的な考え方
医師の8割が処方しているといわれる漢方薬。薬剤師にとっても身近な薬剤となっています。しかしながら、漢方医学独特の診断法や薬剤選択に戸惑うことがあるという声もよく聞かれます。

-
特集
漢方の基礎と臨床 産婦人科における漢方薬の使い方
いまや高齢者医療や緩和ケアなどでも欠かせない存在になっている漢方薬について、産婦人科での使い方を学びます。

-
特集
成人のADHD その特徴と治療までのアプローチ
発達障害の1つ注意欠如・多動性障害(ADHD)はこれまで一般的に小児の病気と考えられてきました。しかし、小児期のADHDをそのまま持ち越して成人になる人が実は少なくありません。

-
特集
薬剤師も知っておきたい水虫の常識
夏になると毎年ぶり返す水虫。 医学的な疾患名は足白癬と言います。 日本人の5人に1人は足白癬、10人に1人は爪白癬であるといわれるほど、 多くの人が白癬に罹患しています

-
特集
妊婦がかかる糖尿病「妊娠糖尿病」の実態とは?
妊娠すると女性の体内では胎児を育てるために糖代謝動態に大きな変化が現れます。「妊娠糖尿病」は妊娠中に発症する、糖尿病には至っていない糖代謝異常のことを言います。

-
特集
妊婦・授乳婦へ薬剤が与える影響とは?
妊婦や授乳婦から薬剤に関する質問を受けて困ったことのある薬剤師は多いのではないでしょうか。妊婦・授乳婦に対する薬剤の影響はエビデンスが乏しいため、医師でも迷うケースは少なくありません。

-
特集
貧血の様々な原因と治療
貧血は様々な原因で発症し、その原因ごとに「○○貧血」という名称で診断・治療が行われます。貧血の原因や種類とその機序、治療法のポイントを解説します。

-
特集
尋常性ざ瘡を知る
青春のシンボルといわれる尋常性ざ瘡(ニキビ)。かつては、疾患としての認識は低く、一般用医薬品で対処していました。今はさまざまな薬剤の開発によって治療レベルが向上しているようです。たかがニキビ、されどニキビ―― 尋常性ざ瘡の薬物治療とは?

-
特集
大腸がんは「患者力」を必要としている
国内の大腸がんによる死亡者数は増加の一途を辿っています。手術が不可能なため薬物療法を実施して延命を計ります。薬物療法の実施時の患者さんとの向き合い方とは?

-
特集
これからふえる、禁煙のおはなし。
禁煙の正しい知識と喫煙者が禁煙治療を行う際の正確なフォローアップについて解説していただきました。

-
特集
乾癬の病態を理解し、臨床に活かす
臨床に活かす乾癬のメカニズムや治療とは!?

-
特集
向精神薬のいま
「向精神薬」超高齢社会で浮き彫りになる課題と薬剤師の関わりとは?