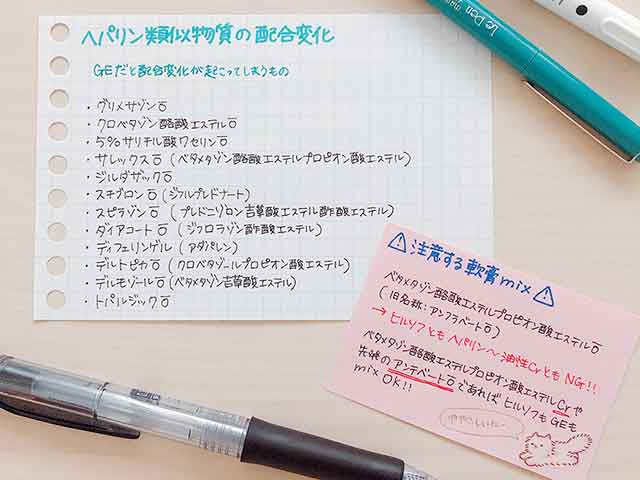Check Point
Part.1 日本人に多いインスリン分泌低下型は病態、年齢によって薬剤を選択
糖尿病患者数は316万人 高齢期に発症リスク高まる
2型糖尿病は、血糖を処理する唯一のホルモンであるインスリンの分泌低下をきたす遺伝因子に、過食や運動不足などの生活習慣が引き起こすインスリン抵抗性が加わって発症する。膵臓の機能が低下すると十分なインスリンが分泌されず、結果として血糖を処理できなくなる。また、インスリンがある程度分泌されているにもかかわらず、その効果が十分でない状態、すなわちインスリン抵抗性は運動不足や過食が大きな要因になっている。
厚生労働省の2014年患者調査によれば、糖尿病患者数は316万6,000人。前回調査(2011年)の270万人から46万6,000人増えて過去最高となった。しかし、これは医療機関で糖尿病の治療を受けている患者数で、無治療のまま放置されている者を含めると、実際の糖尿病患者は1,000万人以上と推計されている。日本人に糖尿病が多い背景には、インスリン分泌能が低いことや過食、運動不足など環境因子がある。また、高齢期には糖尿病の発症リスクが高まることがわかっている。
東京女子医科大学糖尿病センターでは1日350〜400人(年間約20,000人)の糖尿病患者を診療している。糖尿病は全身にさまざまな合併症を併発するが、センター長の馬場園哲也氏によれば、「合併症の症状が出現してから受診される患者さんが多いというのが実情です」という。
合併症はかかりつけ医と専門医が連携して対応
糖尿病は、膵β細胞の破壊にともなう絶対的インスリン欠乏にいたる1型糖尿病と、主に生活習慣に起因して成人期に発症し、インスリン分泌低下、インスリン抵抗性による2型糖尿病、それに膵外分泌疾患や内分泌疾患などにともなって発症するもの、さらには妊娠中に発見される妊娠糖尿病の4型に分類される。1型糖尿病は、主に小児期に発症し、糖尿病全体からみればその頻度は5%程度で、大部分は2型糖尿病である。
糖尿病の診断は、高血糖が慢性的に持続していることを証明することだが、早朝空腹時血糖値≧126mg/dL、75gブドウ糖負荷(OGTT)で2時間値≧200mg/dL、随時血糖値≧200mg/dLのいずれかと、過去1~2ヵ月の血糖値を反映するHbA1cが6.5%以上あったとき糖尿病と診断される(図1)。なお、糖尿病型にも正常型にも属さない境界型は、糖尿病型への進展率が高いことから生活習慣の改善、耐糖能異常の経過観察が求められている。初期は無症状で進行する2型糖尿病の場合、診断される以前から発症している可能性が高く、発症時期を特定することは困難である。
図1 糖尿病の臨床診断のフローチャート
…