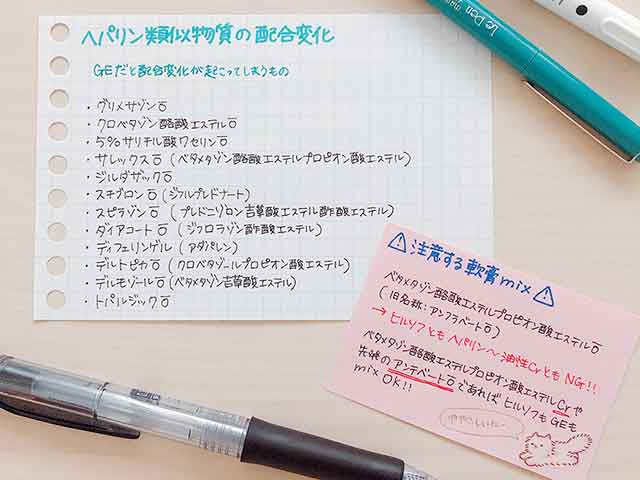薬剤師に期待される服薬指導・薬物治療適正化のポイント
- 抗がん薬における末梢神経障害の訴えは患者によってさまざま。症状を細かく聞くことが重要
- 制吐薬など支持療法では副作用の状況を観察し適切な使用量を守っているか確認する
- ホルモン療法は長期間に及ぶことを説明する
- 患者の訴えをよく聞き、エビデンスに基づいた説明を行う
Part.2 長期にわたる治療を続けるために患者の生活に寄り添った副作用対策を行う
副作用の訴え方は患者ごとに多彩 丁寧な聞き取りが大切
治療薬の進歩や治療の長期化を背景に、がん治療は外来で行うことが増えてきている。聖路加国際病院の場合、乳がん患者は初回から外来で治療を開始することを基本としており、またそれに向けた体制を医療チームで整備している。乳がん治療においては、術前もしくは術後補助療法では約6ヵ月間、再発転移症例においては治療期間の設定がない。したがって、いずれの場合においても長期間にわたって抗がん薬治療を続ける必要があるため薬剤師による外来での服薬指導が重要な役割を果たす。さらには、個人に応じたオーダーメイド医療が進めば進むほど、個々の患者への服薬指導も個別化していくことになる。
「外来で患者さんに接するとき、まず考えなければならないのは感染症対策です。これは乳がんに限らず重要なポイントです」と、同院薬剤部の高山慎司氏は言う。乳がんの場合は、主に殺細胞性の抗がん薬に起因する発熱性好中球減少症(FN)を警戒する必要がある。治療レジメンによってFNの発生リスクは異なるが、万一FNを発症した場合には速やかかつ適切な抗菌薬の投与が必要となる。また、貧血や出血傾向を助長することもあるので、それらの副作用を見逃さないことが求められる。乳がん治療では使用しないが、例えば悪性リンパ腫などで使用されるリツキシマブは液性免疫を低下させるので、B型肝炎既往の患者ではウイルスが再活性化するリスクがある。そのように、使用する薬剤に準じた免疫低下の種類についても把握しておくことが必要である。
次に重要なのは、悪心・嘔吐対策である。抗がん薬使用直後から24時間以内に現れる急性嘔吐、24時間から1週間ほどの間に起こる遅発性嘔吐などがある。例えばアントラサイクリン系の抗がん薬は催吐性リスク分類では高度リスクに分類される。吐き気が起こりやすい抗がん薬を使用するときは悪心・嘔吐の種類に応じた制吐薬が処方される。このような場合、高山氏は「吐き気が強くなってから飲めばいいのか、吐き気が出た時点で飲めばいいのか、患者さんはわからないので、どういう時に、あるいは何時くらいに飲んでくださいと、細かく具体的に説明します」と言う。食前服用の薬でも食後服用してさしつかえない薬剤もあるので、対話の中から患者の生活環境を聞き取り、生活にあった服薬方法を工夫することが大切だ。
タキサン系抗がん薬で気をつけなければならない副作用は末梢神経障害で、しびれには主に感覚障害と機能障害があり、感覚障害にとどまっていれば日常生活への影響は少ないが、手に持っていたペンを落とすなどの機能障害になると日常生活に支障が生じる。
患者はしびれの感覚を「さわさわする」、「ちりちりする」、あるいは「感覚がない」、「ふわふわする」、「砂の上を歩いているようだ」など、さまざまに表現するという。このような感覚が出始めるとQOLが下がるため、支持療法として、漢方薬の牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)やプレガバリン、メコバラミンなどが使用される。
高山氏が経験した50歳代、ステージⅣの女性は、術後再発したためパクリタキセルを3投1休で続けているが、2コース目day15(Total治療回数として6回目)のあたりで指先の違和感を訴えた。その感覚をうまく表現できずに困っていた患者に「うずくような感じですか」と聞くと、「そうです」と打ち解けた表情を見せたという。初期対応として牛車腎気丸を開始したが、症状が悪化傾向であることからプレガバリンの導入について医師に処方提案を検討している。ただ、この患者は就労中であるため、眠気やふらつきなどの副作用が仕事に与える影響を踏まえて患者と相談する予定だという。
ホルモン療法では、ほてりやホットフラッシュなどの更年期様症状を呈する患者が多い。そのような症状が強い場合には、最近では漢方薬による治療を開始するケースが増えている。また薬剤師の重要な役割の一つとして相互作用の確認がある。タモキシフェンで治療中に抗うつ薬のパロキセチンを使用すると効果が減弱し、生存率が低下するというデータがあるため注意が必要だ。
術後ホルモン療法は最低でも5年間の内服治療が必要とされ、近年では10年間の治療を行う場合もある。ここで大事なことは妊孕性の問題である。薬剤によっては催奇形性が報告されているためだ。例えば30歳代前半で乳がんを罹患し、ホルモン療法が必要かつ妊娠を希望する患者の場合、治療中の妊娠は避ける必要がある。エビデンス的には治療中断は避けるべきだが、患者の意志が強い場合、治療の一時中断や卵子凍結などの手段をチーム全体で検討し、患者にとって最善の策を考えるという。患者の中には医師の前では妊娠の希望を伝えられず、後で薬剤師に相談するケースもあるという。
支持療法では薬剤の使用量を確認し適切な副作用管理を心がける
制吐薬や皮膚症状に対する保湿クリームなどは使用量を確認することも薬剤師の大切な役割だ。我慢して使わないケースや使いすぎているケースもあり、患者の副作用の発現状況をよく観察して適切な処方につなげたい。便秘もよく見られる副作用のひとつだが、酸化マグネシウム製剤は相互作用があるため、例えばニューキノロン系の抗菌薬を使用する際には注意し、時間をずらして服用するなどのアドバイスをする。
とくに内服の抗がん薬では、皮膚障害や下痢など副作用が強く出ても我慢して服用し続ける患者がいるという。こうした患者に対して高山氏は「(薬を)減量しても効果が認められています。逆に頑張りすぎると治療を続けられなくなるので、減らすこともある意味で大事なことです」と、エビデンスに基づく治療効果を説明して減量、休薬にもっていく場合もあるという。
Part.1で竹井氏も指摘していた患者の顔が見える医療とは、患者本位の医療、患者が希望する範囲でできうる限りの最善を尽くす医療をさしているのではないか。患者の顔が見える服薬指導を行うために、保険調剤薬局では疑義照会が欠かせない。
高山氏は「カルテが見られないなかで医師の処方意図を理解するのは難しいと思います。DI室を担当していた5年間、当院近隣の保険調剤薬局と勉強会を開催していました。これからも処方意図が分かるような連携を図っていきたいと思います」と話す。