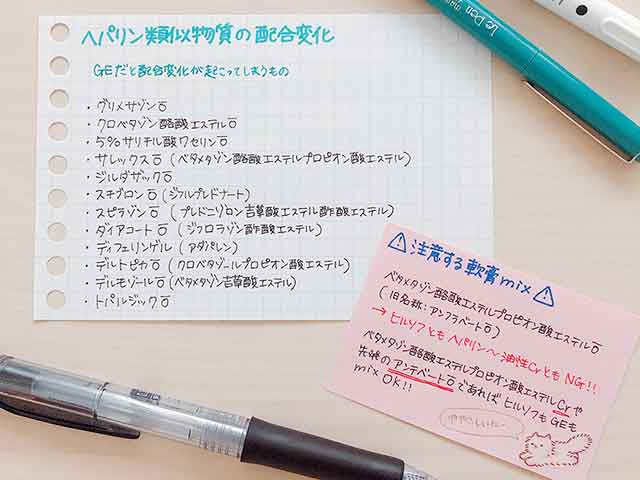Check Point
がん性疼痛には腫瘍に起因する痛みと治療に関連した痛みがある痛みの客観的評価は難しく患者の聞き取りが重要
医療用麻薬の服薬指導では患者の解を解き、正しい知識を伝えることで不安を解消する
神経ブロックや心理療法など非薬物療法にも理解を深める
心不全患者も緩和ケアの対象となる
Part.1 痛みの評価と適切な薬物治療で患者のQOL向上を目指す
がん患者の7割は経過中に痛みを感じる患部、治療、精神の痛みに対処する
疼痛は、その原因により侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛に大きく分類される(表1)。組織の損傷によって炎症が起きると、その情報が脳に伝わり、痛みが認識されるのが侵害受容性疼痛である。傷を保護しようと様々な化学物質が産生される中には、危険を知らせる発痛物質もある。一方、神経障害性疼痛は、知覚神経が損傷することで生じるものである。
| 分類 | 侵害受容性疼痛 | 神経障害性疼痛 | |
|---|---|---|---|
| 体性痛 | 内臓痛 | ||
| 障害部位 | 皮膚、骨、関節、筋肉、結合組織などの体性組織 | 食道、胃、小腸、大腸などの管腔臓器。肝臓、腎臓などの被膜をもつ固形臓器 | 末梢神経、脊髄神経、視床、大脳などの痛みの伝達路 |
| 痛みを起こす刺激 | 切る、刺す、叩くなどの機械的刺激 | 管腔臓器の内圧上昇、臓器被膜の急激な伸展。臓器局所および周囲組織の炎症 | 神経の圧迫、断裂 |
| 例 | 骨転移局所の痛み、術後早期の創部痛、筋膜や骨格筋の炎症に伴う痛み | 消化管閉塞に伴う腹痛、肝臓腫瘍内出血に伴う上腹部・側腹部痛、膵臓がんに伴う上腹部・背部痛 | がんの腕神経叢浸潤に伴う上肢のしびれ感を伴う痛み、脊椎転移の硬膜外浸潤・脊髄圧迫症候群に伴う背部痛、化学療法後の手・足の痛み |
| 痛みの特徴 | 局在が明瞭な持続痛が体動に伴って増悪する | 深く絞られるような・押されるような痛み、局在が不明瞭 | 障害神経支配領域のしびれ感を伴う痛み、電気が走るような痛み |
| 随伴症状 | 頭蓋骨・脊椎転移では病巣から離れた場所に特徴的な関連痛を認める | 悪心・嘔吐・発汗などを伴うことがある、病巣から離れた場所に関連痛を認める | 知覚低下、知覚異常、運動障害を伴う |
| 治療における特徴 | 突出痛に対するレスキュー薬の使用が重要 | オピオイドが有効なことが多い | 難治性で鎮痛補助薬が必要になることが多い |
日本緩和医療学会編『がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン(2014年版)』を参考に作成
急性痛では、痛みのある部位に何らかの炎症が起きていることが多い。傷が治癒するに従って痛みも改善していくが、炎症がある程度落ち着いてきた時期を過ぎても、痛みが遷延しているような場合を、慢性化したと考える。
慢性痛の場合は、侵害受容性と神経障害性の両方の要素が入り交じり、さらに精神的な要素(心因性)も絡んできている。疾患により痛みが持続する期間は様々であり、“慢性”を示す明確な定義はない。概ね急性期を脱して3カ月過ぎても続いているような痛みを慢性痛と考えることが多い。
がんの場合、全体の約7割の患者が罹病中に何らかの痛みを感じると言われており、急性痛も慢性痛もある(表2)。
| 1.がんによる痛み | 内臓痛 体性痛(骨転移痛、筋膜の圧迫、浸潤、炎症による痛み) 神経障害性疼痛 脊髄圧迫症候群 腕神経叢浸潤症候群 腰仙部神経叢浸潤症候群・悪性腸腰筋症候群 |
| 2.がん治療による痛み | 術後痛症候群 開胸術後疼痛症候群 乳房切除後疼痛症候群 化学療法誘発末梢神経障害性疼痛 放射線照射後疼痛症候群 |
| 3.がん・がん治療と直接関連のない痛み | もともと患者が有していた疾患による痛み (脊柱管狭窄症など) 新しく合併した疾患による痛み(帯状疱疹など) がんにより二次的に生じた痛み(廃用症候群による筋肉痛など) |
日本緩和医療学会編『がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン(2014年版)』を参考に作成
急性痛は、がんに起因する痛みもあれば、治療に関連した痛みもある。例えば、腫瘍が大きくなっている場合は、大概は炎症も起きているため痛みを発する。腫瘍が神経を圧迫するとさらに痛みは強くなる。臓器により痛みの感じやすさは異なるので、必ずしもがんの進行状態と比例しない。例えば、肝臓は痛みを感じにくい臓器であり、腫瘍がかなり大きくなっても痛みに気づきにくい。
一方、脊髄神経根の近傍にできた腫瘍の場合、体重をかけるたびに神経が圧迫されるため、病変が小さくても痛みは強烈なことがある。また、骨転移を起こした場合、骨破壊が起こって痛みを生じることがある。
がん治療において、手術、放射線、薬物は三大療法とされるが、いずれの治療も痛みにつながることがある。
放射線療法は、近年は正常組織に対する影響がより少ないピンポイントの照射が主流だが、照射野に粘膜が含まれる場合はどうしても皮膚粘膜の障害を免れず、照射直後から痛みを発することがある。この場合、一時的に鎮痛薬や医療用麻薬の点滴を行うことがある。
また、薬物療法の場合、分子標的薬による末梢神経障害のために手足のしびれや痛みなどを生じることがある。神経障害の程度によっては、治療を終えた後も神経障害性疼痛が続くこともある。
さらに、がんの痛みの場合、精神的な要素はとても大きく、心配ごとが多いほど痛みを強く感じることが多い。一方、患者を支える人たちが周りにいて、ケアがうまく行き届いている場合は、痛みをそこまで感じなくて済むことがある。
痛みは個人差が大きく、客観的な評価が難しいもので、診断は本人の訴えに基づいて行われる。痛みによって生活に支障がある場合、例えば、食事が摂れない、眠れないなど、生活の質(QOL)が悪化しているのであれば治療につなげるべきである。逆に、痛みを抱えていても、本人が困っておらず、生活を支障なく営めることもある。
痛みの最初のスクリーニングにおいては、強さをNumerical Rating Scale(NRS)やVisual Analogue Scale(VAS)などで評価する。例えば、NRS は、痛みを0から10の11段階に分け、痛みが全くないのを0、考えられるなかで最悪の痛みを10として、痛みの点数を問うものである。初期の治療では、アセトアミノフェン、ロキソプロフェンなどの非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)を用いる(図1)。
図1 痛みの評価と対応のフローチャート

日本緩和医療学会編『がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン(2014年版)』を参考に作成
がんでは段階的に除痛を行う薬物治療と心理社会的支援を包括的に
がんの痛みの場合、世界保健機関(WHO)が、3段階除痛ラダーに基づくがん疼痛治療法を定めており、非オピオイド、オピオイドに加えて、鎮痛補助薬、心理社会的支援を包括的に用いる。
さらに、薬物抵抗性の痛みもあり、薬物だけでは不十分な場合は、神経ブロックなどの薬物以外の鎮痛法を、3段階除痛ラダーの適用と並行して検討すべきであるとしている。
がん領域では、必要に応じて医療用麻薬まで用いることが特徴的である(表3)。モルヒネ、オキシコドン、フェンタニルは、すべてμオピオイド受容体に対する作動薬であり、医療用麻薬に指定されている。
| 薬剤群 | 代表薬 | 代替薬 |
|---|---|---|
| 非オピオイド鎮痛薬 | アスピリン アセトアミノフェン イブプロフェン インドメタシン |
コリン・マグネシウム・ トリサルチレートa) ジフルニサルa) ナプロキセン ジクロフェナク フルルビプロフェン※1 |
| 弱オピオイド (軽度から中等度の 強さの痛みに用いる) |
コデイン | デキストロプロポキシフェンa) ジヒドロコデイン アヘン末 トラマドール |
| 強オピオイド (中等度から高度の 強さの痛みに用いる) |
モルヒネ | メサドンb) ヒドロモルフォン オキシコドン レボルファノールa) ペチジンc) ブプレノルフィンd) フェンタニル※2 |
- 日本では入手できない薬剤。
- 日本では経口剤のみ入手可能。
- がん疼痛での継続的な使用(反復投与)は推奨されていないが、他のオピオイドが入手できない国があるため、表に残された薬。
- 経口投与で著しく効果が減弱する薬。
- 原著では、基本薬リストに挙げられていないが、非オピオイド鎮痛薬の注射剤としてはフルルビプロフェンの注射剤(ロピオン®)がある。
- フェンタニルは、経皮吸収型製剤(貼付剤)と注射剤、経口腔粘膜吸収型製剤が使用できる。当時はフェンタニル貼付剤を使える国が限られていたことから、原著では基本薬リストに挙げずに文中での記載にとどめている。
WHO 編『がんの痛みからの解放 第2版』金原出版,1996より
一部改変
オピオイドは、経口投与が困難な場合には個々の患者に合わせて、投与経路や製剤を選択できるようになっている。経口投与製剤にも、錠剤(速放製剤、徐放製剤)、散剤、液剤(内服液)がある。これらの違いを患者にきちんと説明することも重要である。
2017年に登場したヒドロモルフォン塩酸塩(ナルラピド®、ナルサス®)は、モルヒネと極めて構造が似ているが、モルヒネのような活性代謝物を産生しないため、腎機能が低下している場合にも用いることができる“使いやすいモルヒネ”である。
鎮痛補助薬は、それ単体では鎮痛効果を発揮しない薬であるが、鎮痛薬の作用を引き出すような薬で、代表的なものには、抗けいれん薬(ガバペンチン、プレガバリン)、抗うつ薬(SSRI、SNRI、三環系抗うつ薬)などがある。投与の指針など決められたものはないため、段階的に増やしたり、減らしたりしながら効果を見定めていく。近年は、メサドン塩酸塩(メサペイン®錠)のように、オピオイドと鎮痛補助薬の双方の性質を合わせ持った薬物も用いることができるようになっている。
がんにおいてはがんとは無関係の痛み(腰痛や関節痛など)を抱えている場合などもあるため、痛みの原因の鑑別をしなくてはならない。痛みの原因に応じて、通常の慢性痛の治療(神経ブロックなど)も組み合わせていく。
がん以外の痛みの場合、オピオイドを用いることはまれだが、様々な薬を組み合わせてもどうしても痛みが取れなければ条件付きで投与される。
慶應義塾大学病院緩和ケアセンター センター長の橋口さおり氏は、「日本では医療用麻薬に対する抵抗感が強く、処方に対しても心理的なバリアがあります。臨床現場では本当に必要とする人までもが使用を拒否するなど、過剰な抵抗感もあります」と指摘する。
近年は、がんだけでなく良性疾患にも保険適応のあるオピオイドが登場している。患者に対してオピオイドのメリットとデメリットを丁寧に説明し、誤解と不安を解くことも薬剤師の重要な役割だ。
心不全患者も緩和ケアの対象に 多職種チームが連携して介入
緩和ケアは、がん末期の治療というイメージがあるが、WHOはがんと診断した時点での早期の介入を推奨している。がんの疼痛管理は、ペインクリニックなどで対応する慢性痛とは対応の仕方が異なる。慶應義塾大学病院の場合、緩和ケアセンターが診療科から依頼を受けて疼痛管理を行う。
緩和ケアセンターでは、医師、薬剤師、看護師、臨床心理士、管理栄養士などがチームで治療にあたる。最初に痛みだけでなく患者が苦痛と感じるあらゆる症状をスクリーニングして包括的に評価する。
厚生労働省の専門家会議が心不全患者の緩和ケアを推奨すべきとする報告書をまとめ、2018年4月から緩和ケアチームが対応するべき疾患となった。慶應義塾大学病院緩和ケアセンターでも今後は、心不全患者に対しても緩和ケアを実施する方針だ。心機能低下に伴って、末期のがんと同じような息苦しさや倦怠感などの症状を呈することもある。倦怠感は心機能の低下によって不可避であるが、呼吸については、オピオイドを用いることで、息苦しさが軽減されることがあるという。
薬剤師は極めて患者と近く、疼痛管理の鍵となる職種である。薬剤の適切な投与量を見極め、安全性を担保して効果的な使用につながるよう、ガイドラインに精通して、鎮痛薬の使い方や副作用についての正しい知識を備えていることが求められる。
とりわけがん緩和ケアでは、分子標的薬など抗がん剤の副作用として生じる痛みと、その緩和のための薬物治療との双方に精通した薬剤師が求められる。病院内では、病棟はもちろん、化学療法や緩和ケアも外来で行われることが多いため、専門的な薬剤師の働きが重要になっている。
橋口氏は、「薬剤師には、様々な場面でアンテナを巡らし、患者さんがうまく薬を使って症状を取ることができるような手助けをしてほしい。また、保険薬局薬剤師は、患者さんのカルテにアクセスできず、管理に必要な情報を得ることができないというハンディキャップがあるが、薬薬連携などを強化することで力を発揮してほしい」と期待を寄せた。