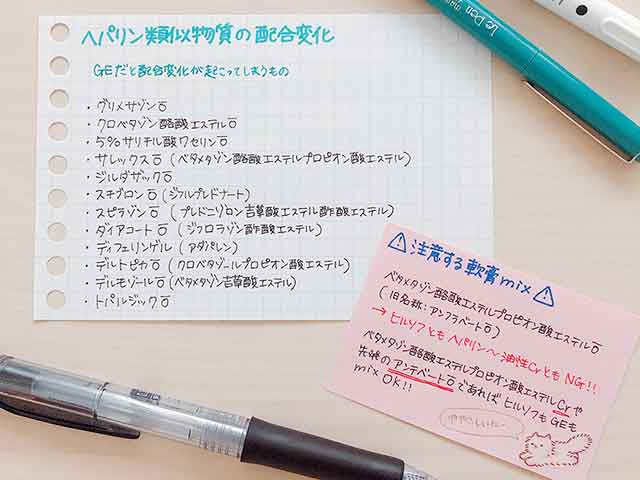Check Point
COPDは循環器疾患、糖尿病などと並ぶ主要な生活習慣病の一つだが、認知率が低く、受診していない“隠れCOPD患者”が多いことが問題治療の柱は「禁煙」「薬物療法」「酸素」。
呼吸リハビリテーションもQOL等を向上させることが証明されている
肺の疾患にとどまらず、さまざまな併存症、合併症があることを前提に、全身疾患として診断・治療する
気管支拡張薬はできる限り治療開始の早期から投与する
治療効果を得るためには正しい吸入方法を継続すること。
薬剤師による吸入指導が重要な役割を担っている
Part.1 早期からの禁煙、薬物療法を継続することで治療効果を最大限に引き出す
喫煙によって起こる“タバコ病” 認知度は低いが患者は漸増傾向に
大規模疫学調査研究NICE study(2001年)によれば、国内のCOPDの患者数は530万人、有病率は8.6%と推定されている。こうした患者のうち、実際に医療機関を受診したのは26.1万人(2014年患者調査)と少なく、疾患の認知率がまだ低いこともうかがわせる。
COPDの年間死亡数(2016年人口動態統計)は1万5,686人(男性1万2,649人、女性3,037人)で、男性では死因の第8位にある。心不全や肺炎死亡者の中にもCOPDを合併した患者が含まれるため、患者数、死亡数ともにさらに上昇すると推測される。
2013年より施行された「健康日本21(第2次)」では、がん、循環器疾患、糖尿病と並ぶ主要な生活習慣病の一つとしてCOPDがあげられ、認知率を10年間で25%から80%にするという目標が定められた。日本呼吸器学会もこの目標数値を掲げ、疾患の啓発に努めているが、残念ながら現在も20%台の低い数字にとどまっている。
COPDは基本的には40歳を超え、かつ長期喫煙歴を持つ人が罹患するもので、40歳以下の喫煙者で発症することは少ない。喫煙することで肺の炎症部位に集まる好中球が増加、活発化し、肺組織を破壊していくことがCOPD発症の背景にある。もう一つには、老化に伴い肺組織の弾性が失われていくことがある(図1)。この2つの背景により、COPDは患者に対して非常に苦痛をもたらすことになる。
図1 COPDの発症

編集部作成
COPDの診断のための肺機能検査
COPDの診断では気道の閉塞性の有無が重要となる。スパイロメトリー(呼吸機能検査)では、最大限に吸気を行い、可能な限り迅速に一気に呼出したときの全体量(FVC:努力性肺活量)、その最初の1秒間の努力性肺活量(FEV1:1秒量)を測定することで、1秒率(1秒量÷努力性肺活量)が得られる。これが70%未満になると明らかな閉塞性があるということで、気流閉塞をきたす他の疾患を除外できればCOPDと診断される。
鑑別診断、病態把握には、X線画像検査、呼吸機能検査、喀痰検査などを実施する。
COPDでは酸素を取り込む肺組織の面積が減っているため、肺拡散能検査によって拡散能(酸素を血液に取り込む能力)の低下を評価する。この低下は喘息では見られない。
胸部単純X線写真では、気腫性病変による肺の破壊の程度や血管の変化などを確認できる(図2)。最近国内で普及してきた胸部高分解能CT(HRCT)では、1〜2mmの厚さのスライス画像から気腫性病変を示す低吸収領域をトレースし、解析結果を見ることができ、病型分類に有用である。
こうした検査を通じて、呼吸機能上から壊れた肺の状態が評価できる。
図2 COPD患者の胸部単純X線写真

肺の過膨張(①横隔膜の低位平坦化、②滴状心)、肺野の透過性亢進・血管影の減少(黒く写る)などが見られる。
提供 大田 健氏
安定期COPDの薬物療法
COPDの治療の柱は、禁煙、薬物療法、酸素である。喫煙を中止しなければ症状はさらに進行するが、禁煙することにより、その後の1秒量の低下速度が減少し、非喫煙者と同程度になることもある。COPDの診断がついたらできる限りすぐに禁煙することが重要である。
かつては治療が困難とされていたCOPDも、現在ではできるだけ早期に薬物療法を開始することに意義があるという状況に変化してきている。『COPD診断と治療のためのガイドライン 第4版』(日本呼吸器学会)では、「薬物療法は患者の症状とQOLの改善、運動耐容能と身体活動性の向上・維持、増悪の予防に有用であるため、積極的に行うべきもの」としている。禁煙を前提として、診断時に患者が維持している肺機能が最大限発揮できるような処方が望ましい。
安定期のCOPDの治療・管理手順を図3に示した。COPDの薬物療法の中心は気管支拡張薬で、主に吸入薬の抗コリン薬とβ2刺激薬、経口薬のメチルキサンチン(テオフィリン徐放薬)がある(表1)。
図3 安定期COPDの管理

日本呼吸器学会「COPD診断と治療のためのガイドライン第4版」を参考に作成
| 薬剤の分類 | 薬品名 | 吸入器 | |
|---|---|---|---|
| 気管支拡張薬 | 短時間作用性抗コリン薬 (SAMA) |
臭化イプラトロピウム | MDI |
| 長時間作用性抗コリン薬 (LAMA) |
チオトロピウム グリコピロニウム ウメクリジニウム アクリジニウム |
DDPI、SMI DPI DPI DPI |
|
| 短時間作用性β2刺激薬 (SABA) |
サルブタモール プロカテロール フェノテロール |
DMDI MDI、DPI MDI |
|
| 長時間作用性β2刺激薬 (LABA) |
サルメテロール ホルモテロール インダカテロール |
DPI DPI DPI |
|
| メチルキサンチン | アミノフィリン テオフィリン(徐放薬) |
(注射) (経口) |
|
| 配合薬 | LABA/吸入ステロイド 配合薬(LABA/ICS) |
サルメテロール/フルチカゾン ホルモテロール/ブデソニド ビランテロール/フルチカゾン |
DPI、MDI DPI DPI |
| LAMA/LABA 配合薬 | グリコピロニウム/インダカテロール ウメクリジニウム/ビランテロール チオトロピウム/オロダテロール |
MDI DPI SMI |
|
MDI:定量噴霧式吸入器、DPI:ドライパウダー吸入器、SMI:ソフトミスト定量吸入器
編集部作成
抗コリン薬は、気道に存在するムスカリン受容体にアセチルコリンが結合するのを阻害して気管支収縮を抑制する。β2刺激薬は、気道の平滑筋のβ2受容体に作用し気管支平滑筋を拡張させる働きを持つ。テオフィリンについては末梢気道の拡張作用や呼吸筋力の増強作用が報告され、低用量では気道の炎症細胞が減少することが示されている。
長時間作用性抗コリン薬(LAMA)と長時間作用性β2刺激薬(LABA)が開発されたことで、COPDの長期管理がしやすくなった。LAMAのチオトロピウム(スピリーバ®)やグリコピロニウム(シーブリ®)などは、1日1回の吸入により24時間気管支拡張作用が持続し、常用量であれば全身性の副作用もほとんど問題ない。LABAも1日1〜2回の吸入で効果を示し、長期間使用しても耐性の出現はほとんどなく、効果も減弱しない。ガイドラインでは、LAMAまたはLABA(必要に応じて短時間作用性気管支拡張薬)が第一選択薬となっている。
早期からLAMAとLABAを組み合わせる テオフィリンを少し加えることも
気管支拡張薬は単剤よりも多剤併用のほうが症状を改善するとされ、効果が不十分な場合、単剤の増量ではなく多剤併用が推奨される。高齢患者の多いCOPDでは、単一デバイスで薬剤の併用を実現する配合薬は利便性が高く、アドヒアランス向上などにも寄与している。
「病態からみると、喘息は平滑筋が収縮して苦しくなり、COPDは肺弾性収縮圧が低下して気道が潰れやすくなっている状態です。こうしたことから、個人的には抗コリン薬を重視していますが、投与開始からβ2刺激薬との配合薬を使ったほうが理にかなっていると考えています。どちらを先にではなく、早い時期から両剤を組み合わせたものを投与することで患者さんがより楽になると思います。ある段階からはテオフィリンの徐放薬も加えます」と国立病院機構東京病院院長の大田健氏。
高齢者へのテオフィリン投与では血中濃度の上昇が懸念されるが、東京病院での1,000人規模の投与実績からは1.5倍程度にとどまっている。「もちろん油断は禁物ですが、400mg程度まではほとんどの患者さんで問題はありません。最初は100mg+100mgの200mgの投与から始め、改善が見られれば増量せず、この時点の血中濃度を計測します。400mgまで増量したほうがさらに改善が期待できるのであれば増量し、血中濃度をモニタリングします」(大田氏)。
なお、急性増悪で入院が必要となる場合、気管支拡張薬だけでは対応しきれないため、全身性ステロイド薬の使用が推奨される。副作用への配慮から、長期間の投与は避けるべきである。
COPDによる慢性呼吸不全には、長期(在宅)酸素療法(LTOT/HOT)も有用である。低酸素状態では肺の血管が攣縮(れんしゅく)を起こし、肺高血圧を引き起こす。一番の特効薬が酸素化で、酸素が潤沢になれば血管が拡張し、肺動脈圧が下がる。また、肺高血圧に対しても種々の薬剤が投与されるようになってきている。
呼吸リハビリテーションについては、肺機能は変わらなくても、呼吸困難の軽減や、QOLおよび日常生活動作(ADL)が向上することが証明されており、肺にも良い影響を与えると考えられる。個々の患者に合わせたリハビリ計画を専門家が設定し、継続することが重要である。
併存症、合併症があることを前提に治療する
COPDの治療にあたっては、併存症・合併症がある状態を前提にしなければならない。例えば、高齢者で前立腺肥大や緑内障がある場合は、抗コリン薬で影響を受けることを理解したうえで投与する。循環器に問題がある場合にはLABAを吸入すると頻脈を起こすなど心臓を刺激する恐れがある。COPDの症状の進行に伴う気胸への対応も重要である。
COPDにおける炎症は肺だけでなく全身性に認められ、栄養障害、骨粗鬆症、骨格筋機能障害、心血管疾患、代謝性疾患などのリスクと関連している。また、日常生活での制限や、禁煙により喫煙習慣を断ち切ることなどが患者の抑うつ状態につながるとの指摘もあり、自殺に注意する必要がある。
COPDは肺がんの重大な危険因子である。COPD患者は、ステージの低い肺がんにもかかわらず肺機能が悪いために手術が難しい例もあり、術後合併症が起こりやすい。
また、COPDの進行期には感染症への注意が必要である。入院して肺炎を治療しても、呼吸機能は階段状に落ちているとされ、症状の増悪にも深く関係している。感染症予防の面からは、インフルエンザや肺炎球菌に対する予防注射を十分に活用すべきであり、ワクチン接種を奨励したい。
喘息とCOPDのオーバーラップ(ACO)では早期に吸入ステロイド薬を投与
従来から、医療の現場では喘息とCOPDの2つの症状が備わった患者の存在が知られてきた。喘息とCOPDの両ガイドラインにも、「喘息とCOPDのオーバーラップ症候群(ACOS)」として記載されている。なお、この疾患名には最近まで「症候群」の文字があったが、独立した新たな疾患が起こっているわけではないので、ACOSから「S」が取れ、ACOの表記が採用されている。
国際喘息ガイドラインである『GINA』(2014)や、COPDの国際ガイドライン『GOLD』(2011)ともにACOを重要視している。国内でも最近『喘息とCOPDのオーバーラップ診断と治療の手引き2018』(日本呼吸器学会)が刊行されたところである。
喘息を主症状としてCOPDを合併している患者は、喫煙歴など喘息以外の所見が検査で分かれば判別可能だが、COPD患者の喘息合併例では、喘息があるのかどうかを見分けるのが難しい。
喀痰中の好酸球が多く末梢血の好酸球も高めであるなど、好酸球性の炎症を疑わせる場合、患者には喘息の要素もあるのではないかと考えて、早めに吸入ステロイド薬を試すべきである。エビデンスは乏しいが、喘息と同様に、大田氏は8週間程度を目安に吸入ステロイド薬を投与して、その効果を評価している。COPDは基本的にコンスタントに息苦しさがあるが、一定の条件が加わるとさらに発作性の苦しさを増すことがあるため、早期投与は重要である。
COPDにおける医療連携のあり方
COPD患者の多くはかかりつけ医にて診療を受けていると推定され、医療連携が特に重要となる。診断には肺拡散能検査やHRCTによる画像検査などが含まれるため、こうした設備のある病院と市中のクリニックが連携して患者を評価したうえで、基本的には主治医(かかりつけ医)が診るのがよいと大田氏は考えている。重症化例では入院や強化した治療が必要な場合もあり、そうした患者は専門医のいる病院で診るという機能分担も必要だ。呼吸リハビリテーションも同様である。
「抗体療法なども検討されており、著効を示す治療法が今後開発されることで連携のあり方は変化していくと思われますが、現状では、病院とクリニックが検査レベルで連携することでより充実した治療を進めることができます」と大田氏は話す。
東京病院の連携医療機関は420施設を超えるが、受入紹介患者の中心は肺炎、肺がんなどで、COPDの患者数自体はそれほど多くはない。清瀬市の医師会、歯科医師会、薬剤師会の三師会は意思疎通が良好に図られ、その中で東京病院も医師会などを交え、随時「東京病院地域医療連携交流会」として講演会などを開催している。また、HOT(在宅酸素療法)患者の会の勉強会開催や、多職種による呼吸サポートチームなどの活動にも取り組んでいる。東京病院は呼吸器中心の専門病院として呼吸リハビリテーションにも強みがあり、同地域の複数の病院と連携を図っている。
服薬指導にあたる薬剤師に求めること
患者本人にとっては、COPDの治療は喫煙という生活習慣を断つことであり、一般には「飲み込む」ものと認識されている薬を「吸い込む」という新しい経験との遭遇である。
薬剤師から吸入薬を患者に手渡して服薬指導を行う場面で、どのように治療への励ましを行うか。また、患者からの疑問等を受けた際に医師との連携をうまく図っていけるかがポイントとなる。チーム医療として制度化するという考え方もあるが、そうしたルールがなくても、かかわる医療者がそれぞれの役割を自ら考えることが治療の成功を左右する。
薬剤師の吸入指導は特に重要で、例えば高齢者ではどのくらいの理解力があるか、どのくらい指の筋力があるかなどを見極めて、個別化した指導を行うことが必要だ。
患者に対しては吸入薬の使用は簡単だということを教えてほしい。吸入薬を継続的に使用してもらうためには、難しい印象を与えてはならない。
「各種調査の結果からも、患者さんは医師よりも薬剤師の先生のほうが話しやすいようです。かかりつけ薬剤師の活動はそうした話しやすい雰囲気を作り出してくれるものだと思います。禁煙指導や吸入指導を通じてCOPDの治療継続の力になっていただきたい」と大田氏は話している。