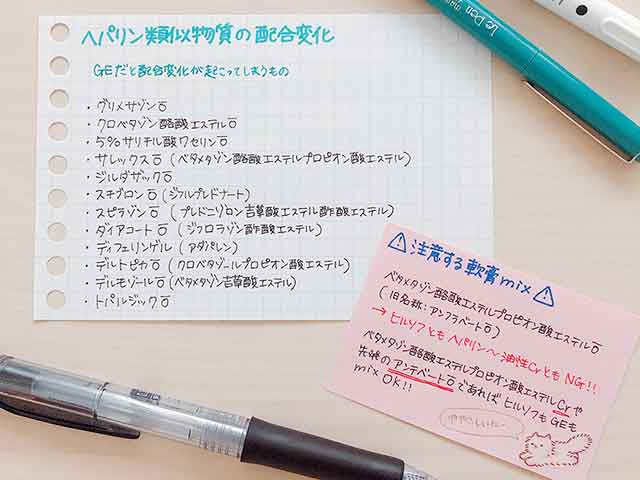抗体医薬の登場とガイドライン改訂で転換期を迎える
皮膚科のコモンディジーズであるアトピー性皮膚炎(AD)の患者は、日本では40万人以上で増加傾向にあり、経過は長期にわたる。2018 年、重症者の治療薬として、初めての生物学的製剤(抗体医薬)であるデュピルマブが承認され、ガイドラインが改訂されるなど大きな転換期を迎えている。京都大学大学院医学研究科皮膚科学講師の本田哲也氏と同医学部附属病院薬剤部の山嶋仁実氏、岡村みや子氏に、AD 治療のポイントを解説いただいた。
Check Point
増悪と寛解を繰り返す慢性疾患保湿と炎症の改善が治療の基本
ステロイド外用薬は病勢に応じ調整する
内服免疫抑制薬の選択と副作用に注意する
新薬の登場で治療選択肢が増えたAD治療抗体医薬は患者の適応を見極めて使用
遺伝と環境が複合的に関与約45万人が罹患
アトピー性皮膚炎(AD)は、皮膚バリア障害と免疫の制御異常による慢性湿疹を特徴とする皮膚疾患で、痒みを伴う皮疹を生じ、増悪と寛解を繰り返すのが特徴である。
先進国ではAD患者は増加傾向にあり、厚生労働省の平成26年患者調査によると患者数は45万6,000人に上る。小児の疾患で成人すれば治るものと考えられがちだが、有病率は4ヵ月~ 6歳で11%前後、20歳~ 30歳代で9%前後と、成人でも一定割合の患者が認められている(アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018)。
発症には、遺伝要因と環境要因が関わっており、前者では、いわゆるアトピー素因が知られている。家族歴、アレルギー疾患の病歴(気管支喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎、アトピー性皮膚炎のうちいずれか、あるいは複数)、IgE抗体を産生しやすい素因を持っていることなどが含まれる。
また、環境要因には、乾燥などにより皮膚のバリア機能が保てなくなっていることがあり、発症予防においても重要である。ADの発症機序については、なお解明されていないことが多いが、病因に基づく分類も試みられており、例えば、内因性と外因性という考え方がある。ほとんどは外因性ADであるが、内因性ADでは金属アレルギーの合併が多く、IgEが上がらないなどの特徴がある。
皮疹は、乳児期では頭、顔に多く、その後、体幹や手足へと拡大していく(図1)。強い搔痒を伴い、一般に季節によって増悪と寛解を繰り返す。乾燥しやすい冬季や春先、あるいは夏の運動時に増悪する傾向がある。典型例では、小児期に発症して、中学生ぐらいになると病勢が落ち着いて寛解に至ることが多いとされる。一方、症状を持ち越すケースもあり、成人で初めて発症する例もある。寛解しても、遺伝要因として、いわゆる敏感肌の体質が維持されることが多い。
図1 アトピー性皮膚炎の臨床写真

提供 本田 哲也氏
臨床症状の数値化と臨床検査値で重症度や病勢を診断
ADに特徴的な臨床症状は、①搔痒、②ADの特徴的皮疹と分布、③慢性・反復性経過の3つで、これらをすべて満たすものは重症度を問わずADと診断される。ただし、ADは発症部位により重症度が異なりそれらの重症度に応じて治療薬が選択されるため、部位ごとの重症度の判定が重要となる。アトピー性皮膚炎診療ガイドラインには、重症度の分類の簡便な方法として、個々の皮疹を、軽度の皮疹または強い炎症を伴う皮疹の2つに分け、それらの体表面積に占める割合によって4段階(軽症、中等症、重症、最重症)に分類する方法などが記載されている。
一方で、ADの病勢診断では、臨床症状の視診だけでなく臨床検査もしばしば行われる。血清IgE値は多くのAD患者で高値を示し、ADの長期的な病勢を確認する際に参考とされる。また、短期的な確認には、末梢血好酸球数や血清LDH値、血清TARC値などが用いられる。中でも、血清TARC値はさまざまな論文でその有用性が示されており、血清LDH値などに比べ病勢を鋭敏に反映する指標であると考えられている。ただし、小児AD患者においては、年齢が低いほどに血清TARC値が高くなる傾向があるなど、年齢によって基準値が異なることは注意すべきとされている。
なお、ADの特徴的な臨床症状である搔痒の評価としては、VAS(visual analogue scale)が有用とされているが、最近では、夜間就寝中の引っ搔き行動を自動的に記録するためのスマートウォッチ用アプリなども開発されている。
治療はステロイドを中心とした外用が基本 内服療法や心身医学的治療も
日本皮膚科学会のアトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018年版では、ADの治療目標は「症状がないか、あっても軽微で日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に到達し、その状態を維持すること」とされている。つまり、まずは速やかに寛解状態へ導き、その状態を維持することがAD治療の基本的な考え方となる(図2)。この考え方に基づき、AD治療では、個々の病態に沿って、①薬物療法、②皮膚の生理学的異常に対する外用療法・スキンケア、③悪化因子の検索と対策の3点が組み合わされて行われている。
図2 アトピー性皮膚炎の診断治療アルゴリズム

日本皮膚科学会編「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018」より転載
ADの薬物療法では、抗炎症外用薬(ステロイド外用薬またはタクロリムス外用薬)で早期に寛解導入を図り、最小限の薬剤で寛解状態を維持することが基本となる。アトピー性皮膚炎診療ガイドラインなどでは、ステロイド外用薬が5つのランクに分けられており(表1)、個々の重症度に応じたランクの薬剤が選択される。ステロイド外用薬では、局所性の副作用として皮膚萎縮や毛細血管拡張、ステロイドざ瘡、ステロイド潮紅、多毛、皮膚萎縮線条などがみられる。ただし、皮膚萎縮線条を除き、多くの局所性副作用は投与中止または適切な処置で軽快する。全身性の副作用についても、強いステロイド外用薬で一部の症例に副腎機能抑制が生じた報告があるものの、適切な使用下での発現頻度は低い。また、もちろんステロイド外用薬の全身性副作用はステロイド内服薬のそれとは異なる。しかし、実臨床ではいまだにステロイドの副作用について外用薬と内服薬で混同されるケースがあり、必要以上の恐怖感や忌避の結果、ステロイド外用薬のアドヒアランス低下につながっている。京都大学大学院医学研究科皮膚科学講師の本田哲也氏は、「ステロイド外用薬の必要性と副作用について丁寧に説明し、適切な使用を促してほしい」と助言する。なお近年では、寛解が導入された後にも抗炎症外用薬を間欠的に投与し寛解状態を維持する「プロアクティブ療法」も行われている。
また、AD治療では抗炎症外用薬としてタクロリムス外用薬も使用されている。タクロリムス外用薬は、ステロイド外用薬とは異なる作用機序を有し、皮膚萎縮といったステロイド外用薬の副作用が懸念される顔面などの皮疹に有用であるとされる。局所性の副作用として、灼熱感や搔痒、紅斑などが確認されている。また、発がんリスクについて、タクロリムス外用薬の使用が皮膚がんやリンパ腫の発症リスクを高めることはないというエビデンスが蓄積されつつある。
これらの抗炎症外用薬のほか、AD治療では保湿外用薬を用いたスキンケアが必須とされる。ADでは、角質層の水分含有量が低下し皮膚の乾燥やバリア機能低下がみられるため、保湿外用薬でバリア機能を回復させ、再燃予防と搔痒抑制を図る。症状によっては、抗ヒスタミン薬やシクロスポリン、ステロイド内服薬、漢方薬などの内服療法が選択されることもある。
シクロスポリンはT細胞に特異的に作用しIL-2などのサイトカイン産生を抑制するカルシニューリン阻害薬で、「16歳以上の既存治療で効果不十分で強い炎症を伴う皮疹が体表面積の30%以上に及ぶ最重症患者」が適応となる。使用中は腎障害や高血圧、感染症などに注意が必要だ。長期使用の安全性は確立されていないため、長期使用では2週間以上の休薬期間をはさみ間欠投与する。難治例が多い京都大学医学部附属病院でもシクロスポリンの内服に至るケースは全体の10%に満たないという。
なお、タクロリムス外用薬とシクロスポリンは妊婦には禁忌となっていたが、厚生労働省は2018年7月に添付文書を改訂し、妊婦への投与が可能となっている。
こうした薬剤による対応のほか、AD治療では悪化因子の検索と対策がきわめて重要となる。食物アレルギーや環境抗原および接触抗原、汗などへの対策が望まれる。さらに、ADでは心理社会的因子が症状に影響する心身相関についても指摘されており、必要に応じて、心理学の専門家と協力し心身医学的治療が計画されることもある。
| 分類 | 一般名 | 商品名 |
|---|---|---|
| ストロンゲスト | クロベタゾールプロピオン酸エステル | デルモベート® |
| ジフロラゾン酢酸エステル | ジフラール®、ダイアコート® | |
| ベリーストロング | モメタゾンフランカルボン酸エステル | フルメタ® |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | アンテベート® | |
| フルオシノニド | トプシム® | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | リンデロン-DP® | |
| ジフルプレドナート | マイザー® | |
| アムシノニド | ビスダーム® | |
| ジフルコルトロン吉草酸エステル | ネリゾナ®、テクスメテン® | |
| 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | パンデル® | |
| ストロンゲスト | デプロドンプロピオン酸エステル | エクラー® |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルム® | |
| デキサメタゾン吉草酸エステル | ボアラ® | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | リンデロン-V®、ベトネベート® | |
| フルオシノロンアセトニド | フルコート® | |
| ミディアム | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | リドメックス® |
| トリアムシノロンアセトニド | レダコート® | |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | アルメタ® | |
| クロベタゾン酪酸エステル | キンダベート® | |
| ヒドロコルチゾン酪酸エステル | ロコイド® | |
| デキサメタゾン | グリメサゾン®、オイラゾン | |
| ウィーク | プレドニゾロン | プレドニゾロン |
日本皮膚科学会編「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018」などを参考に作成
初の抗体医薬デュピルマブ 休薬しつつ効果を見極める
2018年には、AD治療における初の抗体医薬として、デュピルマブが承認された。主にTh2細胞から産生され、皮膚バリアの欠損を引き起こすサイトカイン(IL-4、IL-13)をターゲットとして、その伝達を阻害する「ヒト型抗ヒトIL-4/IL-13受容体モノクローナル抗体」である。
既存治療で効果不十分な成人患者が対象で、初回600mg、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。
適応となるのは、ステロイド外用薬やタクロリムス外用薬などの抗炎症外用薬による適切な治療を一定期間施行しても、十分な効果が得られず、強い炎症を伴う皮疹が広範囲に及ぶ患者である。最適使用推進ガイドラインにおける推奨使用条件のうち病変の範囲をみると、体表面積に占めるAD病変の割合が10%以上と、シクロスポリン(強い炎症を伴う皮疹が体表面積の30%以上)よりも少ない点が特徴だ。
本田氏は、「デュピルマブは完全な薬であるとは言えないが、長期にシクロスポリンを使い続けて、何とか病勢を抑えているような患者には、積極的に切り替えることを検討してもよい」と語る。
治療効果は通常投与開始から16週までに得られるとされ、添付文書では、「16週までに治療反応が得られない場合は、投与中止を考慮すること」と記載されている。デュピルマブの治験にも関わっていた本田氏は、「使用期間と、その後の効果の持続期間は相関するのではないか」という感触を得ている。つまり、1年間使い続けた人は、休薬後1年間程度効果が持続する可能性があるという。
発売以来、京都大学医学部附属病院では、30例近い患者に本剤を使用した実績がある(図3)。症状が抑えられ、保湿外用薬だけで済んでいる人もいるが、効果には幅があり、ステロイド外用薬と併用しているケースも多い。「一定期間使って効果が得られた後は外用剤の使用で再発予防に努め、悪化したらまた使ってみるという使い方も考えられる」と本田氏は提案する。
副作用として、結膜炎が知られているが、頻度は5%未満であり、たとえ発症しても、結膜炎の治療を続けながら、デュピルマブを継続することは可能だという。
今後は、別のサイトカインを標的とした抗体医薬の登場も期待されている。痒みを惹起する物質であるIL-31を標的とした世界初の治療薬、抗 IL-31レセプターAヒト化モノクローナル抗体(nemolizumab)は、京都大学が開発に関わっており、現在第3相試験が実施されている。また、IL-13単独や、皮膚表皮を肥厚させるIL-22を標的とした薬剤の開発も進められている。
AD治療における薬剤師の役割について本田氏は、「ステロイド薬に不安を持っている人は少なくない。良い面・悪い面について、薬剤師さんから説明を補完してもらい、正しい使い方を指導してもらうことはとても有用です」と、期待を語った。
図3 デュピルマブ使用例

提供 本田 哲也氏