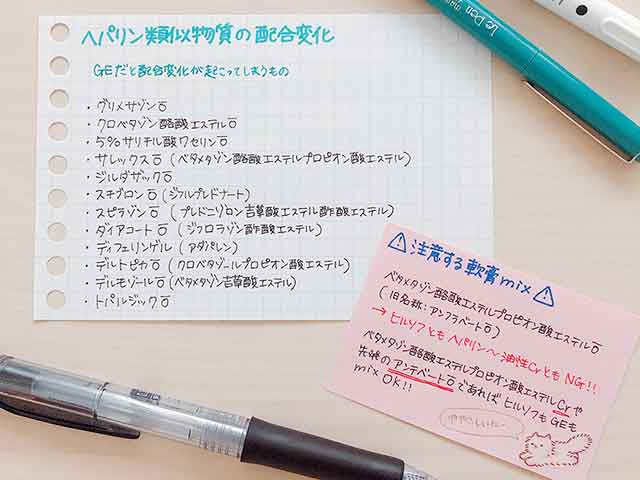手術、抗がん剤、放射線に次ぐ第4の治療法として期待されるがん免疫療法。いくつかの免疫チェックポイント阻害薬の効果が認められ承認されたことで、がん治療におけるがん免疫療法の位置づけは大きく変わりました。今特集では、がん治療の新時代の扉を開いたといわれる、がん免疫療法について、そのしくみや効果に関する基本的な知識、さらにがん免疫療法の最新の情報と課題、そして今後への展望を、慶應義塾大学医学研究科委員長、医学部先端医科学研究所教授の河上裕氏に解説していただきます。
免疫チェックポイント阻害薬の登場でがん免疫療法は新しい時代へ
がん免疫療法とは、ヒトに備わっている免疫防御機構を使って、がんを治そうという治療法です。がん免疫療法の概念は古く、今から120年以上前の1890年代には、がんワクチンの始まりと思われる事例が見られます。その後も研究が続き、非特異的免疫賦活剤、がんワクチン、サイトカイン療法(サイトカインを注射して免疫細胞を活性化する)、モノクローナル抗体療法(ヒトのがん細胞に対する抗体をマウスを用いて作る)など様々な免疫療法が開発されてきました。非特異的免疫賦活剤やサイトカイン療法は体全体の免疫を底上げしてがんと闘うことを目指すものです。がんワクチンは有名ですが、臨床試験ではフェーズⅠ(副作用などの安全性について確認する第Ⅰ相試験)、フェーズⅡ(少数の患者さんで、有効で安全な投与量・投与方法などを検討する第Ⅱ相試験)までは比較的よい結果を出すのですが、フェーズⅢ(多数の患者さんで、有効性を確認する第Ⅲ相試験)で人数を増やすと有効性の有意差が付かないという歴史をくり返してきました。そのため、標準治療になるまでは至っていません。モノクローナル抗体療法は患者さん自身が作る抗体ではないですが、Her2やCD20やVEGFに対する抗体が標準がん治療となっています。
そうした状況が大きく変わるきっかけになったのが、免疫チェックポイント阻害薬の登場です。1990年代に入り、免疫細胞ががん細胞を攻撃するメカニズムが次々と明らかにされると、がん細胞特異的ながん免疫療法の研究が進みました(表1)。なかでも注目されたのが、免疫チェックポイント阻害薬です。2000年代に入って臨床試験が始まると、当初の想定を超えてフェーズⅢでも明確に効くことが示され、一躍注目を集めました。最初の臨床試験は抗がん剤が効かなくなった悪性黒色腫(メラノーマ)の進行がんに対して行われ、治療効果を表す奏効率は約30%ありました。しかも、最初の悪性黒色腫に対する臨床試験では、持続的な治療効果も報告されました。進行した悪性黒色腫であっても約2割に長期生存がみられたのです。米国の臨床試験では、免疫チェックポイント阻害薬の1つであるCTLA-4阻害抗体薬(イピリムマブ)では10年生存率は約20%、抗PD-1抗体薬(ニボルマブ)の5年生存率は34%で、3人に1人は5年以上生存できるという結果が出ています。他の多くのがんでも10〜20%の奏効率が得られています。
| 1893年 | 初の「がん免疫療法」コーリーワクチン臨床使用 (William Coley) |
| 1960年 | 免疫監視機構仮説提唱(Frank M. Burnet) |
| 1988年 | TIL療法によるヒトがん治療効果確認 (Steven A. Rosenberg) |
| 1991年 | ヒトがん抗原同定(Thierry Boon) |
| 1992年 | 免疫チェックポイント分子PD-1遺伝子同定(本庶佑ら) |
| 1995年 | 免疫チェックポイント分子CTLA-4の免疫抑制機構同定 (James P. Allison) |
| 1996年 | CTLA-4抑制による抗腫瘍効果を発見(James P. Allison) |
| 2000年 | 米・抗CTLA-4抗体イピリムマブ臨床試験開始 |
| 2002年 | 免疫編集・免疫逃避機構の解明(Schreiber RD) |
| 2006年 | 米・抗PD-1抗体ニボルマブ臨床試験開始 |
| 2008年 | 日・ニボルマブ臨床試験開始 |
| 2011年 | 米・イピリムマブ承認(悪性黒色腫) |
| 2012年 | 米・ニボルマブ第Ⅰ相臨床試験結果発表 |
| 2014年 | 日米・ニボルマブ承認(悪性黒色腫) |
| 2015年 | 日・ニボルマブ適応拡大(非小細胞肺がん) 日・イピリムマブ承認(悪性黒色腫) |
| 2016年 | 日・ニボルマブ適応拡大(腎細胞がん、ホジキンリンパ腫) 日・ペムブロリズマブ承認(悪性黒色腫、非小細胞肺がん) |
| 2017年 | ニボルマブ適応拡大(頭頸部がん) |
週刊医学界新聞 医学書院 第3207号を改変
がん免疫療法が注目されている理由としては、①他の薬が効かなくなった様々ながんの患者さんでも一定の割合(10~30%)で明確な治療効果を示す、②しかも人によっては比較的持続的な効果が得られるかもしれない、という2つが挙げられます。従来のがん免疫療法における腫瘍縮小効果は期待できないが、標準治療後の再発予防や延命ぐらいならば可能かもしれないという考え方から、本当に効くがん免疫療法は進行がんに対しても有効であることが明らかになり、臨床の場でのがん免疫療法の位置づけが一変したのです。今多くの製薬メーカーは、免疫療法の開発に力を入れ始めました。10年前には考えられなかったことです。
ただその一方で、免疫療法が効くというのが強調されすぎることによる誤解や弊害が生じています。現時点でも多くのがんでの奏効率は10~30%であり、実は効かない症例のほうが多いのです。より効果を上げるためにはどうしたらよいか。世界中で今、研究が進められています。
まずは免疫について知ろう!自然免疫と獲得免疫とは?
まずは、免疫のしくみについて説明しておきましょう。
免疫とは、病気を引き起こす細菌やウイルスなどの異物から体を守るしくみの総称です。ヒトの免疫は、自然免疫系と獲得免疫系に大別されます。まず自然免疫系が働き、その後に獲得免疫系が働きます。
獲得免疫
獲得免疫で重要な役割を担っているのは、リンパ球のT細胞とB細胞です。抗原特異性と多様性、免疫記憶と呼ばれるメモリー機能を持つことが特徴ですが、抗原特異的なリンパ球が爆発的に増えて強力な効果を生み出すことが重要です(図1)。
図1 T細胞を例にした獲得免疫の特徴

玉田耕治著「やさしく学べる がん免疫療法のしくみ」羊土社を参考に作成
なかでもがん免疫療法のしくみに深く関わるのはT細胞です。T細胞はその細胞表面にT細胞受容体(T cell receptor : TCR)を持っており、このTCRを介して細菌やウイルスなどの異物がもつ目印(抗原)を認識することで活性化します。この目印に特異的な反応を「抗原特異的」と呼びます。また、私たちの体内に存在するT細胞はそれぞれ異なるTCRを持ち、その数は10の十数乗にも及ぶとされます。これが「多様性」で、ありとあらゆる抗原に対応できます。「免疫記憶」は予防接種を考えるとわかりやすいでしょう。子どもの頃に麻疹ワクチンを接種しておけば、大人になっても麻疹にかからずに済みます。これは、麻疹ワクチンを目印として記憶したT細胞(メモリーT細胞)が、長期間にわたって体の中に存在し続けるからと考えられています。ある感染症に一度かかると二度とかからないのは、免疫記憶があるからです。
B細胞はその細胞表面に抗原特異的に反応するB細胞受容体を持ち、それが細胞からはずれて抗体となり、様々な異物に反応します。例えばインフルエンザの抗体はウィルスを除きます。
自然免疫
自然免疫系を担っているのは、好中球、マクロファージ、樹状細胞などの貪食細胞やNK細胞などです。細菌やウイルスなどの異物が入ってくると、まずは自然免疫系が働き、好中球などの白血球が食べて異物を排除します。食べて全部排除できればよいのですが、それだけでは抑えられないので、その後に獲得免疫系が働きます。その際、自然免疫と獲得免疫の橋渡し役になるのが樹状細胞です。樹状細胞は体のあちこちにあり、がんであれば、壊れたがん細胞の破片を取り込み、攻撃するべき細胞の目印(抗原)をT細胞に提示するという役目を担っています(詳細は後述)。
がんと免疫の関係 免疫監視機構を逃れてがん化!
この免疫防御機構をがんにどう効かせるかが問題です。細菌やウイルスなど外から入ってきた異物に対しては強い免疫反応が起こるので排除できますが、がん細胞はもともと自分の細胞が遺伝子異常(人間の体の設計図であるDNAに傷がついたり〔塩基配列の変異〕や遺伝子の発現異常が起こる)を起こして増殖したものです。通常、正常な細胞は互いにくっつくと制御し合って増殖が止まります(接触阻害)が、DNA異常でその調節がきかなくなると、その細胞は無限に増殖するがん細胞に姿を変えていきます。体内ではがん細胞の元になる遺伝子の異常をもつ細胞が生み出されています。
遺伝子異常が起こる原因としては、紫外線、放射線、タバコ、発がん物質などの外因性要因と、細胞分裂時に偶然起こるDNAのエラーや活性酸素によるダメージなどの内因性要因があります。一般的には、がんは喫煙や紫外線など外因性要因によって起こると思われがちですが、DNAのコピーエラーなどの内因性要因によるものが多いとの報告もあります。
さて、私たちの体内では遺伝子異常をもつ細胞が生まれていますが、それがそのままがんになるわけではありません。遺伝子修復などの様々な体の防御機構がありますが、その一つとして免疫監視機構と呼ばれるしくみが、がんの発生を防いでいます。樹状細胞はがん細胞の一部を貪食すると、がん細胞内のタンパク質をアミノ酸約10個からなる短いペプチド(抗原)に分解し、それをHLA(ヒト白血球抗原)と呼ばれる細胞表面分子を介して、細胞外に提示させます。T細胞上のTCRは抗原ペプチドを細胞表面で提示するHLAとの複合体を認識し、活性化します。がん細胞の場合、ペプチドはがん抗原と呼ばれ、それに反応するT細胞ががんを攻撃するキラーT細胞となります。
一方、がん細胞も生き残りをかけて巧妙な罠を仕掛けてきます。T細胞に認識されるタンパク質を出さずに獲得免疫を逃れたり、免疫にブレーキをかけるタンパク質を作って、免疫の働きを抑えたりします。こうしてがん細胞が増殖していきます。さらに、がんが増殖するにつれて、がんの組織内でがん細胞自体も変化して、免疫による排除や治療が難しくなっていきます。
通常、体は異物が入ると反応して免疫が活性化されますが、活性化されたままだと体が壊れてしまうので、普通の状態に戻るための免疫抑制機構(ブレーキ)があります。また、免疫が自分の体を壊さないように抑えるシステム(自己免疫寛容)も備えています。これがうまく働かなくなって起こるのが自己免疫疾患です。がん細胞は、本来有害な免疫反応を抑えるためのブレーキである免疫抑制機構を働かせて、免疫防御機構から逃れていることがわかってきました。がん細胞は、体に備わっている免疫を抑える機構を「悪用している」のです。実際、臨床で見られるがん細胞は免疫抵抗性や抑制性を獲得していることが観察されています。
免疫チェックポイント阻害薬 そのしくみと効果は?
がん免疫療法は大きく分けると2種類あります。①がんに対する免疫を強める「アクセルを踏む」方法と、②がん細胞がかけた免疫の「ブレーキを外す」方法です。前者には、がんワクチン療法、サイトカイン療法、培養T細胞を用いた養子免疫細胞療法(後述)などがありますが、ごく一部のサイトカイン療法や非特異的免疫賦活剤以外には、有効性や安全性が確立されて標準治療になっている方法はありません。明確ながんに対する治療効果が明らかになっている免疫チェックポイント阻害薬は後者です。
免疫のブレーキ役の1つが、免疫チェックポイント機構です。免疫チェックポイント機構に関わる分子には、T細胞上に発現するPD-1、CTLA-4などがあります。がんは、免疫から逃れられるような特殊な環境(がん微小環境と呼ばれる)を形成しており、その微小環境を構成するがん細胞やマクロファージなど細胞表面には、PD-L1という膜タンパクが発現することがあります。PD-1とPD-L1は鍵穴と鍵のような関係にあり、結合するとT細胞の機能にブレーキがかかってしまいます。CTLA-4とペアになるのは抗原提示細胞上のCD80/86という分子です。
免疫チェックポイント阻害薬として使われているのは、免疫チェックポイント分子に結合してブレーキをかける機能を阻害するモノクローナル抗体で、抗PD-1/PD-L1抗体、抗CTLA-4抗体があります。これらの抗体が免疫チェックポイント分子同士の結合を阻害することで免疫に対するブレーキを解除し、T細胞ががん細胞を攻撃できるようにします(図2)。
図2 がん細胞がT細胞の働きを止める仕組みと抗PD-1抗体薬の働き

河上裕 監修 「もっと知ってほしいがんの免疫療法のこと NPO法人キャンサーネットジャパン」 2016年を改変
PD-1/PD-L1阻害薬治療では、最初は悪性黒色腫のみだった適応は、肺がん、腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、頭頸部がんへと広がり、さらに胃がんなど、さまざまながん種で臨床試験が進んでおり、一定の治療効果が示されつつあります(表2)。
| 標的とする分子 | 抗体の一般名 | 対象となるがん(承認済み) |
|---|---|---|
| CTLA-4 | イピリムマブ | 悪性黒色腫 |
| PD-1 | ニボルマブ | 悪性黒色腫、非小細胞肺がん、腎細胞がん、 ホジキンリンパ腫、頭頸部がん |
| ペムブロリズマブ | 悪性黒色腫、非小細胞肺がん |
2017年6月時点の情報に基づいて作成
最近は、免疫チェックポイント阻害薬がどんな人に効くかも徐々にわかってきました。DNAの異常は大きく分けて、①遺伝子に傷が付くパターン、②エピジェネティクスといって、環境などによってDNAの塩基配列の変化を伴わずに遺伝子の発現が変わっていくパターンの2つがあります。このなかで、遺伝子に傷が付いてアミノ酸が変わったためにがん細胞にだけ発現するペプチド抗原が、がんを攻撃するT細胞の標的として重要であることがわかり、免疫チェックポイント阻害薬の効果にも関係します。
遺伝子に傷が付く場合、がんの増殖、浸潤、転移に関わる「ドライバー変異」と、がん細胞の増殖などとは直接関係のない「パッセンジャー変異」に分けられます。たとえば、分子標的薬はがんだけに起こっている遺伝子異常に対して、それをピンポイントで叩くように作られます。分子標的薬の開発者は、ドライバー変異のような、がんの増殖に関与する遺伝子を見つけて、そのタンパクに対する阻害薬を開発します。
一方、パッセンジャー変異は、傷はたくさん付いていても、その傷自体は細胞の異常増殖にあまり関係がなく、昔はゴミのような、何もしていない変異と考えられていました。ところが、免疫チェックポイント阻害薬によってパッセンジャー変異が改めて注目を集めることになりました。免疫チェックポイント阻害薬を投与した後、がんに特異的なT細胞が増え、それががん細胞を排除してくれます。そのターゲットはいろいろありますが、なかでも重要なのが、パッセンジャー変異が起こったところのタンパクであることがわかってきました。最近はこれを「ネオ抗原」と呼んでいます。今まではなかったが、DNAが傷ついたせいで新しくがん細胞特有のタンパクが作られ、それが免疫チェックポイント阻害薬を投与したときに標的になって、T細胞が活性化されます。逆に言うと、ネオ抗原を持っていない人には免疫チェックポイント阻害薬が効きにくい可能性があります。前述したように奏効率は悪性黒色腫で10~30%、他の多くのがんではたかだか10~20%です。効かない人のほうが多いのです。
免疫チェックポイント阻害薬が効かない人への対応が課題
このように免疫チェックポイント阻害薬が効く人の理由が一部わかってきました。一つは遺伝子にたくさん傷が付いて、T細胞のターゲットとなるネオ抗原が多いタイプが効きやすいことです。同じがん種でも、患者さんによってDNA変異の数は個人差があります。変異が10個しかない人もいれば、3000個ある人もいるなど千差万別なのです。たとえば肺腺がんの場合、喫煙者はDNA変異が多く、こういう人はT細胞のターゲットもたくさん持っているので、免疫チェックポイント阻害薬が効きやすい傾向にあります。
逆に効きにくいのはDNA変異が少ないがんです。肺がんでは、非喫煙者の肺腺がんで、EGFR遺伝子やALK遺伝子変異などのドライバー変異で起こったがんは、喫煙や炎症などによって長い期間をかけて多くのDNA変異をもつ肺扁平上皮がんと異なり、DNA変異が少ない場合が多く、免疫チェックポイント阻害薬が効きにくい場合が多いです。逆に、このようながんでは、ドライバー変異をターゲットとしたゲフィチニブなどの分子標的薬が効きます。
その一方で、遺伝子に傷がたくさんあっても必ずしも効かないこともわかっています。傷、すなわちT細胞のターゲットが存在しても、他の因子のためにがんを攻撃するT細胞ががんの中に入ってこれない状態などの問題があり、免疫チェックポイント阻害薬が効かない場合も多いことが分かっています。その問題のしくみはさまざまで、これをうまく除く方法があれば、それを併用することによって、免疫チェックポイント阻害薬を効くように変えることができるかもしれません。肺がんの約80%、悪性黒色腫の約60%は、がん細胞に対するT細胞が十分に誘導されていないので、この場合、免疫チェックポイント阻害薬に他の治療法をプラスする(複合がん免疫療法)ことで、免疫チェックポイント阻害薬単独では効かない人を効くようにしようという研究が世界中で行われています。すでに米国を中心に数百の臨床試験が進行中で、一部では併用による治療効果の増強が認められています。
単剤免疫療法から複合的免疫療法へ T細胞利用免疫療法も期待
抗がん剤治療では多剤併用療法が一般的ですが、免疫療法も複合免疫療法によりさらに高い効果が得られることが期待されています。現在、臨床試験で明らかになっているのが抗PD-1抗体と抗CTLA-4抗体の併用です。悪性黒色腫の場合、抗PD-1抗体単独で治療すると奏効率は3割程度でしたが、抗CTLA-4抗体を併用すると奏効率は6割程度になったと報告されています。これは、免疫に対してブレーキを解除する薬同士の組み合わせです。
免疫療法同士だけでなく、従来の標準がん治療である、化学療法、分子標的薬、放射線治療との併用も多数試みられています。これらは、投与の量や方法によって、単にがん細胞を障害するだけでなく、免疫反応を活性化させる作用のあるものも報告されています。現在、さまざまな複合免疫療法で、治療効果が上がる可能性が報告されており、今後、さらなる評価により、承認されていくと考えられます。
一方、免疫チェックポイント阻害薬が効かない症例や苦手とするがんでは、がんを特異的に認識するT細胞を体外で培養して投与する養子免疫細胞療法も進められています。悪性黒色腫と子宮頸がんでは、腫瘍浸潤T細胞を培養したTIL療法の効果が示されていますが、他のがんではうまく行かず、がん抗原を認識する受容体を人工的に作成して、その遺伝子を導入したT細胞(TCRT, CART)を用いた養子免疫療法の開発も進められています。
がん免疫療法は副作用が問題 今後の課題は?
がん免疫療法で問題になるのは副作用です。免疫チェックポイント阻害薬は免疫のブレーキ機構を解除する治療法なので、がんに対する免疫力は上がりますが、場合によっては自己免疫疾患のような副作用が起こります。そのため、抗がん剤治療とはまったく違った副作用が多く観察され、あらゆる臓器に様々な自己免疫反応による症状が生じる可能性があります(図3)。間質性肺炎、心筋炎など重篤な副作用もあり、大腸炎、重症筋無力症、甲状腺機能異常、1型糖尿病などさまざまな自己免疫反応が起こり、臓器を障害します。今までの抗がん剤とまったく違う副作用が予測不能で起こるので、早期発見、抗体の中断、免疫抑制剤の使用など早期の対応が必要です。そこで免疫チェックポイント阻害薬を使うときは、患者さんも含めて全ての医療従事者が免疫のしくみの概略を勉強し、なぜこのような副作用が起こるのかを理解したうえで使用し、対応することが大切です。
図3 免疫チェックポイント阻害薬の副作用として予測される症状

河上裕 監修 「もっと知ってほしいがんの免疫療法のこと NPO法人キャンサーネットジャパン」 2016年を改変
現在、免疫チェックポイント阻害薬が効く可能性が高いのかどうかなど、がん患者さんの免疫状態がどのような状態にあるかを評価できるようなバイオマーカーの研究が世界的に進められています。がんは人によって免疫の状態が違います。免疫チェックポイント阻害薬が効きにくい人に投与しても無駄になり、効く人にはしっかり使えばよいので、そのためにも効く人と効かない人を見分けるバイオマーカーの開発が重要課題となっています。またいつまで投与すべきかを判定する指標を見つけることも課題になっています。
がんの薬物治療ではすでに、その人に合った薬を使う「個別化医療」が進んでいますが、がん免疫療法も同じで個別化医療の実現が重要と考えられます。同じがん種であっても患者さんごとに生じている遺伝子変異が異なります。がん細胞の遺伝子変異は免疫療法の効果にも関係します。患者さんごとにがん免疫状態を評価して、より適切な免疫療法を行えるようになる(precision medicine, personalized therapy)ことが今後の目標です。