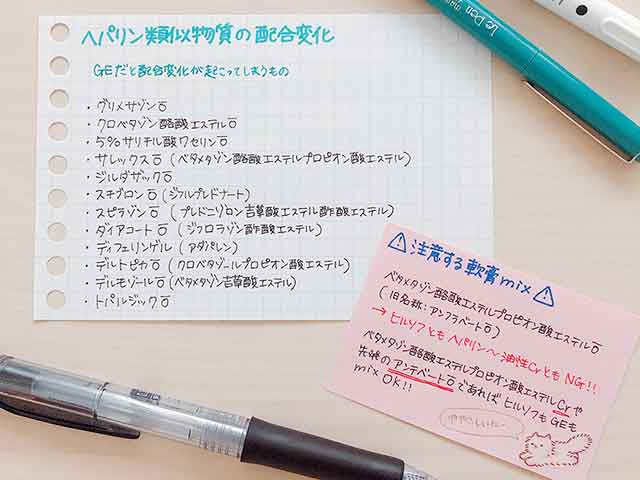2024年2月号特集「薬剤耐性(AMR)対策 抗菌薬による治療を失ってはいけない」に続き、AMR対策の実践編を特集します。抗菌薬を含めた抗微生物薬の適正使用が推進されるなか、「抗微生物薬適正使用の手引き」も改訂を重ね、2023年には一般外来のみならず入院患者の基本的な指針も追加されました。入院患者編も含め基本的な考え方や現場での対応について、国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 総合感染症科 医長(AMR臨床リファレンスセンター 主任研究員)早川 佳代子氏に解説していただきました。
抗微生物薬適正使用の手引きの改定 入院患者編が加わる
「抗微生物薬適正使用の手引き」(以下、手引き)は2017年に第一版が発行され、2019年には乳幼児編が加筆され第二版が発行されました。主に外来診療を行う医療従事者を対象に、一般外来における基礎疾患のない患者に対する指針が「成人・学童期以降の小児編」と「乳幼児編」でそれぞれ記載されました。日本で使用されている抗微生物薬の多くは経口抗菌薬であり、使用量の多い抗菌薬が外来で処方されていると考えられることから、急性気道感染症や急性下痢症を中心に、外来診療での抗微生物薬の必要性の有無を判別することに主眼が置かれました。
2023年に発行された第三版では、医療機関で入院患者の診療にたずさわる医療従事者を対象とした入院患者編が加筆されました。別冊「入院患者の感染症で問題となる微生物」では、感染症診療を専門とする医療従事者や、院内の抗菌薬適正使用支援チーム(AST:Antimicrobial Stewardship Team)を含む医療従事者を対象に、より具体的な治療が解説されています。入院患者編での具体的な処方例は、腎機能が正常な成人患者を対象としています。さらに詳細なエビデンスは補遺に記載されており、今後、入院患者編のダイジェスト版も発行が予定されています(表1)。
| 2017年:第一版 |
|---|
| 「抗微生物薬適正使用の手引き」第一版 策定 |
| 2019年:第二版 |
| 乳幼児編の項目を新たに加筆 |
| 2023年:第三版 |
|
入院患者編の項目を新たに加筆。別冊、補遺の発行。 別冊「入院患者の感染症で問題となる微生物」 補遺(入院患者における抗微生物薬適正使用編) (入院患者編ダイジェスト版の作成・公開が予定されている) 厚生労働省 「薬剤耐性対策(AMR)について」のページからPDF形式でのダウンロードが可能となっている(2024年2月現在) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120172.html |
厚生労働省 薬剤耐性(AMR)対策について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120172.html)より作成
- 本記事では成人・学童期以降の小児期についての解説としておりますが、抗微生物薬適正使用の手引き第三版では、乳幼児期のパートもあります。
急性気道感染症は症状から4つに分類される
急性気道感染症には、急性上気道感染症(急性上気道炎)および急性下気道感染症(急性気管支炎)が含まれ、「風邪」、「感冒」などとも言われます。「風邪」は、さまざまな意味をもつため、患者さんが風邪をひいたと訴えて受診した場合には、急性気道感染症なのかどうかを鑑別することが必要です。
手引きでは、抗菌薬が必要な症例と不必要な症例を見極めるために有用な米国内科学会の分類に基づき、鼻症状(鼻汁、鼻閉)、咽頭症状(咽頭痛)、下気道症状(咳、痰)から、急性気道感染症を、①感冒、②急性鼻副鼻腔炎、③急性咽頭炎、④急性気管支炎の4つに分類しています(表2)。
| ❶感冒 |
|---|
|
| ❷急性鼻副鼻腔炎 |
|
| ❸急性咽頭炎 |
|
| ❹急性気管支炎 |
|
抗微生物薬適正使用の手引き第三版をもとに作成
ウイルス性の急性気道感染症には抗菌薬投与は推奨されない
感冒はウイルス性の急性気道感染症であり、抗菌薬の投与は推奨されていません(表3)。ただし、症状の悪化が進行性であったり、いったん軽快しつつあった症状が再度増悪するときには二次的な感染症の合併の可能性を考慮します。
| ❶感冒 |
|---|
|
| ❷急性鼻副鼻腔炎 |
|
【成人】
【学童期以降の小児】
|
| ❸急性咽頭炎 |
|
| ❹急性気管支炎 |
|
抗微生物薬適正使用の手引き第三版をもとに作成
急性鼻副鼻腔炎の場合、軽症例への抗菌薬の投与は推奨されておらず、成人の中等症または重症例、学童期以降の小児で遷延性または重症例にはアモキシシリンの投与が推奨されています(表3)。症状が二峰性に悪化する場合には細菌感染症を疑います。急性咽頭炎や急性気管支炎の原因の大部分はウイルスで、急性咽頭炎でA群β溶血性連鎖球菌が検出された際には、抗菌薬としてアモキシシリンが推奨されています(表3)。
急性下痢症の大部分はウイルス性
急性下痢症は、発症から14日間以内に軟便または水様便の排便回数が普段よりも1日3回以上増加している状態とされています。急性下痢症の90%以上は感染性で、吐き気、嘔吐、腹痛、腹部膨満、発熱、血便、テネスムス(便意が頻回に生じるしぶり腹)などを伴うことがあります。胃腸炎や腸炎と呼ばれることもあり、嘔吐に対して下痢が目立たないこともあります。非感染症の急性下痢症は、薬剤性、中毒性、虚血性などです。
急性下痢症のほとんどはウイルス性で、ノロウイルスやロタウイルスが代表的です。加熱が不十分で汚染されている二枚貝を食べた場合や、ヒトからヒトへの感染があります。2日間を超えて発熱がつづく場合には、ウイルス性の急性下痢症以外の疾患を考慮します。
原因が細菌の場合は、非チフス性サルモネラ属菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌、ビブリオが代表的で、海外からの帰国者では腸管毒素原性大腸菌、カンピロバクターのほか、赤痢菌やコレラ菌がみつかることもあります。最近の抗菌薬投与歴がある場合、クロストリディオイデス・ディフィシル腸炎の可能性も考慮します。
急性下痢症で嘔吐が目立つ場合にはウイルス性の感染症や毒素による食中毒を疑いますが、集団発生のケースであれば、ウイルス性の場合は潜伏期間が14時間以上、食中毒では2~7時間ですので、潜伏期間の違いが両者の鑑別に役立つでしょう。
急性下痢症は自然に軽快することが多いため、脱水を防ぐために水分摂取をすすめるなどの対症療法が主体になります(表4)。
| 急性下痢症 |
|---|
|
抗微生物薬適正使用の手引き第三版をもとに作成
入院患者の症状や検査から感染症の原因を特定する
入院患者での発熱の原因としては感染症が最も多いことから、まずは感染症の可能性から考えていくことが必要です。入院患者での主な感染症は、肺炎、手術部位感染症(SSI)、腸管感染症、尿路感染症(UTI)、血流感染症などで、臓器特異的な臨床所見を確認するとともに、培養検査の実施も必須です(表5)。
| 肺炎* | 尿路感染症(UTI) | 腸管感染症 | カテーテル 関連血流感染症 (CRBSI) |
創部感染症 (褥瘡感染や手術後のSSI) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床所見 | 咳・痰、呼吸音の異常、呼吸数増加、動脈血酸素分圧(PaO2)低下、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)低下 | 背部痛や肋骨脊柱角、叩打痛があれば急性腎盂腎炎を疑う(症状がみられない場合も多い) | 食欲低下、腹痛、下痢(初期には下痢を認めないことがある) | カテーテル刺入部の発赤があれば感染を疑う | 創部からの排膿、創部の発赤、腫脹、熱感、疼痛 |
|
臓器診断に 必要な検査 |
胸部X線、 必要に応じ胸部CT |
尿中白血球定性、 尿沈渣 |
特になし |
血液培養 2セット |
浅部SSI:肉眼所見 深部SSI、臓器・体腔SSI:エコー、CT検査など |
|
微生物診断に 必要な検査 |
痰グラム染色、痰培養 |
尿グラム染色、 尿培養 |
CDIの項目を 参照する |
血液培養 2セット |
創部滲出液や膿汁のグラム染色、培養。臓器・体腔から無菌的に採取された液体または組織のグラム染色・培養 |
|
想定される 原因微生物 |
口腔内のグラム陽性球菌、黄色ブドウ球菌、 グラム陰性桿菌 |
グラム陰性桿菌、 腸球菌 |
CDI | 表皮ブドウ球菌、黄色ブドウ球菌、グラム陰性桿菌、カンジダ |
表層:メチシリン感受性黄色ブドウ球菌(MSSA)、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、表皮ブドウ球菌、 深部:黄色ブドウ球菌、グラム陰性桿菌 体腔臓器:グラム陰性桿菌、嫌気性菌、腸球菌、カンジダ |
CDI:クロストリディオイデス・ディフィシル感染症 、SSI:手術部位感染症 *人工呼吸器関連肺炎(VAP)含む
抗微生物薬適正使用の手引き第三版、早川氏の話をもとに作成
感染症を疑って検査を行ったものの検査結果としては感染症ではなかった場合、感染症以外の原因による発熱を考慮します。入院患者さんの発熱のおよそ1/4は感染症以外が原因という報告もあります。感染症以外の発熱として、薬剤熱、結晶性関節炎、血栓などが代表的です。
薬剤熱では原因となる薬剤の投与中止が解決策です。結晶性関節炎の代表として「偽痛風」が知られています。偽痛風は患者さんの膝などの関節にピロリン酸カルシウムが貯留し炎症を起こすことで発熱しており、NSAIDs等でのコントロールが必要となります。そのほか、深部静脈血栓症など血栓による微熱の持続や、担癌患者さんでの腫瘍熱などを経験することもあります。
一歩踏み込んだ培養検査が適切な抗菌薬の選択につながる
入院患者さんの感染症は、感染症科だけでなく多くの診療科で対応されています。感染症専門医が介入していても、していなくても、適切な培養の実施がなければ適切な抗菌薬を選択することは困難です。抗菌薬投与前と広域抗菌薬への変更前には血液培養や感染臓器に合わせた培養(例:肺炎なら喀痰培養、尿路感染症なら尿培養)を採取することが重要です。
血液培養は発熱しているときに採取するもの、という意見をお聞きすることもありますが、発熱がなくても血液培養が陽性になる(菌血症や敗血症を起こしている)状況はあり得ます。表6にあるような経験的治療を考慮する状況や原因不明の炎症反応高値などでも血液培養を採取することは極めて重要です。
| 体温 |
|
|---|---|
| 呼吸数 |
|
| 血圧 |
|
| 脈拍数 |
|
| 意識レベル |
|
| 食事量 |
|
| 悪寒、戦慄 |
|
| 血糖値 |
|
qSOFA:quick Sequential Organ Failure Assessment
抗微生物薬適正使用の手引き第三版、早川氏の話をもとに作成
発熱はなかったもののCRP高値の精査目的で採取した血液培養からMRSAが陽性になった事例は複数例経験があります。特に高齢者などですと発熱がないこともあります。血液培養では、検体を2セット採取していただくと陽性率が上がりますし、培養で出てきた菌が原因菌か汚染菌かも判別しやすくなります。また、入院72時間以上経過してから発症した下痢症では、便培養ではなくクロストリディオイデス・ディフィシル感染症(CDI)の鑑別のためにCDトキシン(GDH)検査を行います。
急を要する状態ではエンピリック治療から開始する
入院患者さんは、外来患者さんに比べるとより重症な基礎疾患などを持っている場合が多く、高齢の患者さんも多くいらっしゃいます。そのため、培養検査の結果が出る前、すなわち確定診断の前でも、治療が必要かどうかの判断が直ちに求められることがあります。特に、敗血症を疑う状況では可能な限り早めに治療を開始した方がよいケースもあります。
こうした緊急性の高い場合、想定される原因微生物に対して効果のある抗菌薬を使用し、経験的治療(エンピリック治療)を開始します。バイタルサインとしては、「原因不明だがハァハァと呼吸している(頻呼吸)」、「血圧が普段より低い」、「脈拍が早くなり脈拍数が収縮期血圧を上回ってきた」といった点に注意を払います。
また、高齢者では意識レベルや食事量の変化がみられることもあります。「入院時には問題なく会話ができていたのに急に変なことを言うようになった」、「毎日ごはんを食べていたのに急にごはんを食べなくなった」、さらに、あまり寒い日ではないのに「毛布を持ってきてほしい」など寒気を強く訴えて布団にくるまって寝ている患者さん(悪寒)や毛布にくるまっているのにブルブル震えているような状況(戦慄)は敗血症のリスクが高く、すぐに抗菌薬治療を始めた方がよいと考えられます(表6)。
耐性菌が想定される患者ではスペクトラムを広めに考慮
エンピリック治療でも、なるべくスペクトラムの狭い抗菌薬が使用できればよいのですが、培養検査や薬剤感受性検査の結果が分からない段階では、適切な抗菌薬の選択が難しいことがあります。入院期間が長い患者さんや介護施設の患者さんなどは薬剤耐性菌による感染症の可能性もあることから、エンピリック治療ではスペクトラムが狭すぎる抗菌薬を選択しない方がよいでしょう。そのほかの判断基準としては、CRBSI(末梢静脈ライン、中心静脈ライン、動脈血ライン、透析カテーテルなど)であれば皮膚から入ってくる菌、尿路感染症であれば腸管内に存在する菌などが原因微生物として想定されますので、それにより抗菌薬の選択を検討します。
72時間で評価し抗菌薬の適正化をはかる
感染症を疑ってエンピリック治療を開始した後には、治療の適正化が必要になります(表7)。治療開始からおよそ72時間で評価が可能になるため、その時点で必ず治療効果の評価を行います。細菌培養の結果で細菌感染症の証拠がなければ、抗菌薬の中止を検討します。培養検査の結果、原因菌が想定できればその細菌をカバーする狭域スペクトラムの抗菌薬へ変更します。狭域化のことを、”de-escalation“や”narrowing“ということもあります。
狭域化を行う理由は、広域抗菌薬の過剰使用は患者や集団で薬剤耐性菌が生じるリスクを高めてしまうこと、また、感染症ごとの第一選択薬である狭域抗菌薬ではない薬剤を使用することで、治療が不成功となるリスクも高めてしまうためです。
| 治療効果の評価 |
|---|
|
| 抗菌薬の中止、変更 |
|
ESBL:extended-spectrum β-lactamase;基質特異性拡張型βラクタマーゼ
抗微生物薬適正使用の手引き第三版、早川氏の話をもとに作成
治療効果が不十分なときは多角的なアセスメントを
感染症の治療期間を決めるときには、患者背景、感染臓器、原因微生物を考慮します。治療効果が不十分なときには、薬剤耐性菌を想定して抗菌薬の変更を検討することも多いか思いますが、実際には抗微生物薬のスペクトラムが問題ではないこともあり、原因のアセスメントが肝要です。
治療効果の判定時期や指標は適切か、抗微生物薬のスペクトラムや投与方法に問題がないか、患者さんが免疫不全ではないか、遠隔部位の感染や新たな感染がないか、感染症以外の原因はないか、などを考慮し、必要に応じて微生物学的検査や画像検査も実施します。
静注から経口へ切り替えのメリットと条件
入院患者の初期治療は静注の抗菌薬投与が多いものの、経口薬剤でもバイオアベイラビリティに優れたものは静注の薬剤と同等の抗菌効果を期待できることが多く、経口薬への切り替えにも多くの利点があります(表8)。ですから、切り替えが可能な症例では積極的に経口薬を検討します。
経口薬への切り替え可能な条件としては、臨床症状が改善し24時間38℃未満の解熱が維持され呼吸・循環動態が安定していること、静注抗菌薬による治療継続が必要でないこと、適切な経口抗菌薬の選択肢があり、経口または経鼻胃管の服用が可能で十分な吸収が見込まれること、外来などでは患者が中断せずに服薬を継続できることなどです。
抗菌薬を投与するためだけに点滴ルートが確保されている患者さんもいますので、安全に経口薬に切り替えることができるのであれば、切り替えによってカテーテル感染のリスクも減らせると思います。経口薬へ切り替えられる可能性について医師が気づいていないケースもあり、すでに食事がとれているといった患者さんの状態や、吸収が良好な経口抗菌薬の選択肢があるといったことなどを、薬剤師さんから医師へ伝えていただくことも、切り替えにおいて役立つと思います。
| 切り替えのメリット |
|---|
|
| 切り替えのパターン |
|
抗微生物薬適正使用の手引き第三版、早川氏の話をもとに作成
未来への影響を考慮しつつ現場の効率化も工夫する
抗菌薬の適正使用は、公衆衛生上の課題として、AMRの観点から必須です。AST活動も推進され、診療報酬として感染対策向上加算も新設されました。一方で、ASTの仕組みが導入されてからは、広域抗菌薬の処方後監査やフィードバックなど、感染症診療に携わる薬剤師さんの業務負荷が増えている印象もあります。
各科の医師は目の前にいる患者さんの状態を改善するために必死に取り組んでいます。そうした現場の医師とは別の視点で、薬剤師さんが抗菌薬に関するさまざまな提案やサポートを実施いただけることは非常にありがたく理想でもあります。しかし、その取り組みが薬剤師さんの日々の業務負担になる可能性は大きいと思います。AMR臨床リファレンスセンターでは、抗菌薬の使用量の把握にも活用できるJ-SIPHE(Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare Epidemiology:感染対策連携共通プラットフォーム)や診療所版J-SIPHE「OASCIS(Online monitoring system for antimicrobial stewardship at clinics:診療所における抗菌薬適正使用支援システム)」などのシステムも提供しています。半自動化や効率化によって少しでも薬剤師さんの業務軽減にご活用頂ければ幸いです。





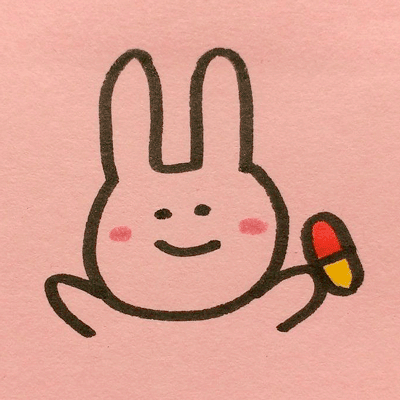
.jpg?1710295025)