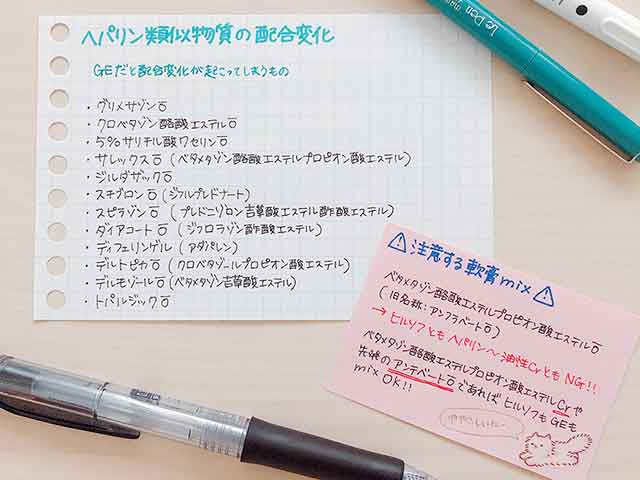川崎病とは
川崎病は4歳以下の乳幼児期に好発する原因不明の血管炎症候群です。発症年齢のピークは1歳弱で、成長とともに罹患率は低下しています。
疫学的には、患者数は女児よりも男児のほうが1.3〜1.5倍くらい多いといわれています。また、父親や兄弟に川崎病の既往歴がある男児に発症する、つまり同胞発症が多いことがわかっています。さらに夏と冬に発症することが多く、春と秋には少ないという季節的な特徴も見られます。
1979年、1982年、1986年と過去に3回、爆発的に患者数が増加した流行がありましたが、その後患者数は右肩上がりに増えています1)。小児科医に川崎病についての知見が広がり、川崎病と正しく診断される患者さんが増えているためともいわれていますが、この増加傾向の原因についても明らかにはなっていません。
合併症と重篤な後遺症
多川崎病の臨床症状は、2~3週間で自然に消失します。そのため1967年に日赤中央病院(現・日本赤十字社医療センター)の小児科医で医学博士の川崎富作氏がこの疾患を初めて報告した当初は、良性の疾患と考えられていました。
ところが罹患した患者さんが突然死する事例が多発しました。これらの死亡事例を調査したところ、心臓に栄養を送る冠動脈に瘤(こぶ)が生じて血流が滞った結果、血管に血の塊ができ、心筋梗塞を起こしていたことがわかりました。その後の調査によって、川崎病にはさまざまな合併症が起こることがわかってきました。ただ、それらの多くは適切な処置を行えば重篤にならず、後遺症も残りません。しかし、前述のような心臓の合併症の場合、命に関わります。そのため、後遺症として冠動脈瘤が残った場合には、心筋梗塞予防の服薬治療や、重篤な際には狭心症や心筋梗塞が起こるためカテーテル治療などを行わなければならないこともあります。
診断の決め手になる特徴的症状
川崎病には、①高熱、②両眼の結膜の充血、③口唇と口腔が赤くなり、「いちご舌」が発現、④全身に不定形の赤い発疹、⑤手足の浮腫、⑥頸部リンパ節腫脹、といった6つの臨床症状があり(図)、そのうちの5つが該当すると確定診断となります。しかし、これらの症状が一度に出現するわけではありません。
川崎病は汎血管炎、つまり全身の血管に炎症が起こる疾患で、血管の炎症とは、いわば血管の火傷です。全身の血管に火傷が起こるため、高熱が出ます。ただし、高熱を発する疾患はほかにもあるので、川崎病のエキスパートでも高熱だけでは診断できません。高熱が続き、数日の経過で前述したさまざまな症状が現れることによって初めて川崎病と診断することができます。特徴的なのは手足の変化で、発赤を伴う浮腫が急性期の四肢末端の症状として見られますが、一般的な浮腫と違って川崎病の場合は硬くパンパンに張って押してもへこみません。そして2週間くらい経つと、手の皮が指の先からむける膜様落屑(まくようらくせつ)が見られます

結膜の充血

口唇の紅潮と「いちご舌」

不定形発疹

手の紅斑と浮腫
川崎病の検査と急性期の治療
症状が出現してから「7病日以内に診断」し、「10病日以内に熱を下げる」ことが、後遺症を残さずに治療を完了するための大切な要素です。
かかりつけの医療機関で川崎病が疑われた場合、患者さんは当センターのような専門医療機関に紹介され、診断が確定します。重症度や合併症の有無などを調べるために、心エコー検査と血液検査は欠かせません。
急性期の治療目標は、血管の炎症をできるだけ早い段階で抑え、冠動脈瘤ができるのを予防することです。現在は12〜24時間の持続点滴による大量免疫グロブリン投与と服薬によるアスピリン投与を併用するのが標準治療になっており、入院での治療が必要です。
免疫グロブリンは、体重1kgあたり2gを投与します。例えば体重10kgの患児の場合の投与量は20gとなります。アスピリンは、少ない投与量の場合には血管内で血液がかたまるのを防ぎ、多量の場合には血管の炎症を抑える効果があります。急性期には体重1kgあたり30mgが投与量の目安とされていて、熱が下がってからは5mgに減らします。
大量免疫グロブリン投与は1980年代後半から始まった治療法ですが、非常に効果があり、冠動脈瘤の発生や、それが引き金になって心筋梗塞になる重篤な例が著しく減少しました。
しかし、大量免疫グロブリン投与とアスピリン投与でも熱が下がらないケースが患者数全体の15〜20%くらいで見られます。これらのケースに該当する患者さんは、免疫グロブリンやアスピリン治療が効きにくいタイプです。熱が下がらないと血管の炎症が続くため、冠動脈瘤ができるリスクが高まります。このような場合、これまでは免疫グロブリンの再投与やステロイド投与などの追加治療が行われてきました。しかし現在は、あらかじめ免疫グロブリンやアスピリンが効きにくいタイプと予想されるケースには、免疫グロブリンとアスピリンに加えて、ステロイドを初めから投与する強化治療を行うようになっています。
免疫グロブリンの効きにくさ(不応例)の判定には、血清Na、治療診断病日、ASTなど7項目からなるリスクスコアを用い、11点満点中5点以上であれば強化治療の対象とします。このリスクスコアは「川崎病急性期治療のガイドライン」にも採用されています。
こうした治療法の進歩により、冠動脈瘤の発生頻度は年間に川崎病を発症する患者さんのうち2%程度にまで低下しました。
冠動脈瘤が残った場合の治療
川崎病の治療は大きく2つの段階にわけられます。急性期の血管の炎症を鎮める治療と、遠隔期つまり熱がおさまった時期に行う冠動脈瘤に対する治療です。
経過にしたがって川崎病の主な症状は消失しますが、冠動脈瘤ができてしまった場合には、血栓をできにくくしたり、溶かしたりする治療などが行われます。つまり、この段階からは川崎病の治療ではなく、冠動脈瘤の治療となります。
8mm未満の冠動脈瘤には、チクロピジン、ジピリダモールなどの抗血小板薬によって、血液をサラサラにして血栓をできにくくする治療を行います。8mm以上の巨大冠動脈瘤となると、血栓ができやすく心筋梗塞などが起こりやすいので、抗血小板薬だけでは十分な効果が得られません。そこでワルファリンカリウムなどの抗凝固薬を用います。
いずれも血栓予防の治療ですが、血栓ができてしまった場合には、ウロキナーゼやアルテプラーゼなどを用いて血栓を溶かす治療が選択されます。
フォローアップと薬剤師への期待
小さい冠動脈瘤の場合は、経年変化で瘤が消失して血管が正常化することがあります。その場合は、薬を服用する必要がなくなります。しかし巨大冠動脈瘤ができた場合には、抗血小板薬と抗凝固薬の服用を継続しなければなりません。さらに心事故を予防するために食事や運動などに関する生活指導も必要になります。
患者数が増加傾向にあるということは、川崎病の既往歴のある成人が増えているということでもあり、その中には幼い頃から抗血小板薬と抗凝固薬の服用を継続しながら成長してきた患者さんもいます。すると成長とともに新たな課題が出てくることが少なくありません。例えばワルファリンカリウムには催奇形性があることが知られているので、妊娠を希望する女性の場合には計画妊娠が必要です。また、思春期に差し掛かると服薬コンプライアンスを十分に守ることができず、心筋症や狭心症が起きやすくなることもあります。このような時期になる前に適切な服薬指導を患者さん本人と家族に行っていくことはとても大切です。
加えて免疫グロブリンの既存治療に効果不十分な急性期の川崎病患者さんを対象にインフリキシマブや免疫抑制剤シクロスポリンが使用されることもあり、今後さらに新しい治療薬が登場してきます。こうしたさまざまな治療薬について、効果と安全性を医師とともに薬剤師が患者さんと家族に説明して理解を深めてもらうことが、健やかで高いQOLを維持しながら日々を過ごしていくために重要となるのです。
参考文献
- 第24回川崎病全国調査成績:川崎病全国調査担当グループ
http://www.jichi.ac.jp/dph/kawasakibyou/20170928/mcls24report.pdf - 日本川崎病学会:http://www.jskd.jp/info/photo.html