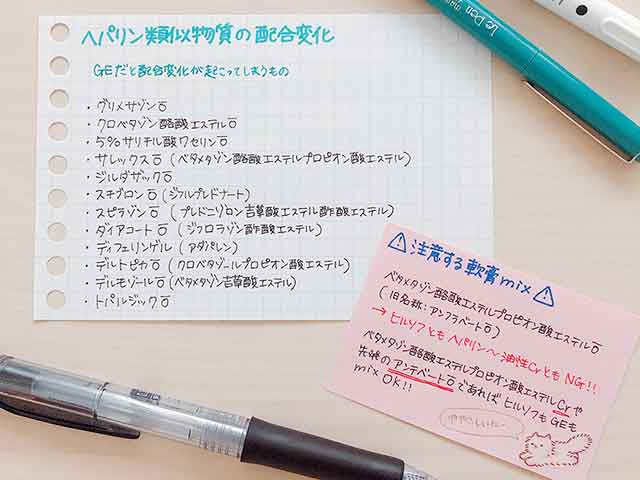SLEの症状の一つとして生じる腎炎
ループス腎炎とは全身性エリテマトーデス(SLE:systemic lupus erythematosus)によって生じる糸球体腎炎です。
患者さんが受診する診療科としては、膠原病科と腎臓内科などがあります。後者を受診するのは、当該医療機関に膠原病専門医がいない場合やループス腎炎になって初めてSLEと判明した場合などが多いようです。腎臓内科を受診している場合にも、腎臓の治療を受けながら原疾患であるSLEの治療も併せて受けることになります。
SLEは体内で生じるさまざまな自己抗体を介した免疫反応が多臓器に障害をきたす慢性の炎症性疾患です。私たちの体には外から入ってきた異物である細菌やウイルスなどから防御する免疫システムがあります。これは外敵と闘うシステムであり、自分の体を攻撃するためのものではありません。ところがSLEの場合は自分の体を攻撃して全身の臓器に炎症を起こすのです。
SLE患者さんの約半数が2年以内にループス腎炎に
現在、国内のSLE患者数は約5万人と推定されています。患者さんの男女比は1:9で、発症するのは20~30歳代の女性に多いのが特徴です。妊娠・出産の時期と重なることから、女性ホルモンが疾患の発症や増悪に関連しているのではないかと考えられています。
かつては5年生存率が30〜50%で、治療にも長期入院を余儀なくされるなど、患者さんの予後や生活に大きな制限がありました。しかし、現在は薬でのコントロールがうまくいくようになり、10年生存率が90%を超えており、入院が必要になっても2週間などの短期で、寛解維持とともに通常の就学・就労などの生活ができる慢性疾患といえるでしょう。
ループス腎炎は、SLEによって生じるさまざまな症状の一つです。多くの場合、SLEの症状は発熱、関節痛、皮疹などから始まります。腎臓の障害はSLE患者全体の約50%に見られるのみで、SLEの患者さん全員がループス腎炎になるわけではありません。また、ループス腎炎はSLEの発症時から2年以内に起こることが多く、SLEと診断されて10年以上経ってからループス腎炎になるケースは余りありません。また、二つの腎臓は片方だけということはなく、自己抗体や免疫複合体は血流に乗って運ばれるのでループス腎炎になるときは二つ同時です。
なお、以前は血圧の治療薬などでループス腎炎に似た症状を呈する「薬剤性ループス」になる方がいましたが、これはループス腎炎とは違います。また、近年はこうした副作用の多い降圧薬はほとんど使われなくなりました。
糸球体という“ザルの網目”が傷むと悪化
腎臓は全身をめぐる血液を濾過し、老廃物を尿として体外へと排泄します。この濾過機能を担っているのが、毛細血管のかたまりである糸球体です。ループス腎炎により炎症が起こると、細かいはずのこの血液濾過器の“ザルの網目”が粗くなります。すると本来は通り抜けないはずのタンパク質が粗い網目を通過して尿として排泄されてしまいます。通過する際に糸球体を傷めるのでさらに網目が粗くなり、ついには濾過器自体が破壊され働かなくなります。この状態が腎不全です。
末期腎不全になると透析が必要になり、患者さんの生命予後やQOLに大きな影響を及ぼします。したがって、SLEの患者さんに対しては血液検査や尿検査などで腎臓の様子を観察し、ループス腎炎の予防はもちろんのこと、早期発見、早期治療を行う必要があるのです。また、最初の自覚症状はむくみが多いのですが、SLEの診断が先についていて、定期的な検査をしていれば症状が出る前に診断がつくことがほとんどです。
血液検査では血清クレアチニンやアルブミンなどの数値で腎機能を確認します。クレアチニンは体内でエネルギーとして使われたタンパク質の老廃物で、腎臓で濾過されて尿中に排出されています。ところが腎機能が低下すると、尿中への排泄量が減り、結果として血液中に溜まるので、血清クレアチニン数値が高くなります。
アルブミンは肝臓でつくられるタンパク質で、浸透圧を調整する働きもしています。腎機能が低下して尿にアルブミンがもれ出てしまい、血液中のアルブミン濃度が低くなると、血管内の浸透圧が落ちて血管外に液体成分が流れ込むため患者さんにはむくみの症状が出ます。
尿検査では、タンパク尿や尿沈渣を調べます。尿中にタンパクが多いのは腎の濾過機能の異常を示し、尿に白血球や赤血球が混じっているのは糸球体に炎症や出血があることを示しています。
ループス腎炎の疑いがある場合、治療反応性などを決めるクラス分類のために、腎臓を細い針で刺して組織を採取する腎生検という検査が重要です。
ステロイドと免疫抑制剤で治療
ループス腎炎の治療は薬物療法を基本とし、寛解導入期と寛解維持期に分けて行います(図)。寛解導入は、活動性の腎炎を積極的に治療し、短期間で蛋白尿を改善させ腎機能を正常化させる治療です。導入期の治療が奏効して寛解したら、それを最低限の薬剤で維持するような治療を行います。これが寛解維持期の治療で、大きな再発を防ぎながら薬剤の副作用を最低限にすることが主眼となります。
図 ループス腎炎のステロイドと免疫抑制剤による治療方法

American Journal of Kidney Diseases 2014; 63(4): 667- 676を参考に作成
第一選択薬として用いられるのは糸球体の炎症を抑えるステロイドですが、症状が改善したら徐々に減らしていき、必要に応じて免疫抑制剤を併用します。さらに足がつるなどの副作用症状を緩和する補助療法として漢方薬を用いることもあります。
近年の治療で用いられている免疫抑制剤は、ミコフェノール酸モフェチル(MMF)、ミゾリビン、アザチオプリン(AZA)、タクロリムス水和物、シクロホスファミド水和物(CYC)、シクロスポリン(CYA)などです。また、特筆すべきはヒドロキシクロロキンの登場でしょう。抗マラリア薬として半世紀前に開発されたのですが、膠原病などにも効果があることから、SLEの世界的標準治療薬として、広く使用されていました。日本では、かつて似た作用機序と化学構造を持つクロロキンによる網膜症が問題となりましたが、ヒドロキシル基により血液網膜関門の通過性が制限され、安全性が向上した薬剤です。しかしながら、稀ですが網膜症などの副作用が報告されているので、使用に際しては適切な用量を用いることと、定期的な網膜のスクリーニングが必要です。また、稀ではありますが低血糖の副作用が報告されており、服用時は車の運転などに注意するように指導することが添付文書に記載されています。
若い患者さんの妊孕性温存と薬の禁忌
若い女性の患者さんが多いことから、妊娠・出産の妨げにならないような薬剤選択を必要とする場合もあります。タクロリムス水和物、AZA、CYAなどはガイドラインで妊娠中に使用可能な薬剤とされており、添付文書改訂の要望が出されている薬剤です。例として、日本産科婦人科学会のガイドラインでも「特定の状況下では妊娠中であっても投与が必須か、もしくは推奨される」となっています。添付文書を鵜呑みにせず、薬剤については常に最新情報の確認が必要といえるでしょう。
ヒドロキシクロロキンは、催奇形性の報告もなく、妊娠中は有益性投与が認められていますが、本邦では添付文書で授乳中の投与は認められていません。欧米では本剤を中止するとSLEの症状再燃の危険が高いので、継続して使用されることが通常です。
また妊娠を望む患者さんには、催奇形性のためMMF、ミゾリビンは禁忌です。CYCは催奇形性に加え、早期閉経の原因になるので、妊娠を望む患者さんには出来る限り使用を避けます。