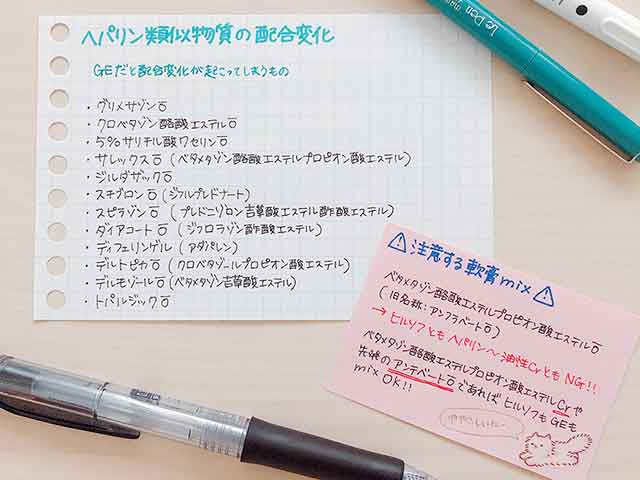関節リウマチは、1970~1980年代、適切な治療をしないと患者の半数は10年後に日常生活が不自由になるという認識だった。
慶應義塾大学医学部内科学教室リウマチ内科教授の竹内勤氏は、2010年以降、関節リウマチの治療戦略が大きく変わったことで、寛解導入が向上したことについて言及した。関節リウマチの治療目標は、厳格なコントロールによって、臨床的(関節炎)寛解を達成し、さらに構造的(関節破壊)寛解、機能的(身体機能障害)寛解を目指すようになった。目標達成に向けた治療(treat to target)で関節リウマチの患者の予後は改善されることになったが、その立役者は生物学的製剤だ。慶應義塾大学病院ではアダリムマブの早期導入によって構造的寛解は66%を達成したという。
竹内氏は、寛解100%の可能性を示唆するとともに、副作用、免疫原性などを今後の課題としてあげ、「世界の趨勢は早期診断・治療に向けて進んでいる。次の時代の治療薬に期待したい」とまとめた。
一方、消化器領域では炎症性腸疾患である潰瘍性大腸炎、クローン病に対して生物学的製剤が使われている。いずれも原因不明で根本的な治療法が確立していない。炎症性腸疾患の治療は約20年前までは潰瘍性大腸炎に対してプレドニゾロンと5-ASA、クローン病に対して絶食による栄養療法が主流だった。
北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センターセンター長の日比紀文氏は、腸の炎症を持続させる機序として、①炎症を起こすサイトカイン、②免疫細胞の接着・浸潤、③微生物との反応、④上皮の損傷・組織の破壊を指摘した。
しかし、2010年、炎症性腸疾患の治療でも抗TNFαモノクローナル抗体の登場によってパラダイムシフトが起きた。難治性の潰瘍性大腸炎、クローン病は早期から生物学的製剤を使って炎症を抑えることで外来での治療が可能になり、腸管切除術を回避することができる。その結果、患者は通常の日常生活を送ることが可能になった。
「生物学的製剤の発達で寛解導入・維持が容易になり、今後は炎症を完全に抑え、無症状のまま日常生活を送れるような治療を目指していく」と日比氏は述べた。
乾癬は、皮膚の紅斑、肥厚、鱗屑が特徴的な症状で、患者の身体的・精神的QOLを低下させる慢性の炎症性疾患だ。社会福祉法人聖母会聖母病院皮膚科部長の小林里実氏によると、患者のおよそ3割は関節症状を伴い、関節破壊を起こす可能性がある。
国内の乾癬治療の歴史は古く、1940年代はタールと紫外線による治療が中心だった。その後、ステロイド外用薬、免疫抑制剤などを経て、抗TNFαモノクローナル抗体の登場で乾癬治療は劇的に変わった。生物学的製剤で、全身の皮膚症状の90%以上が消退し、重症度を評価するPASIスコアは95%以上の改善率が得られるという。
現在(2018年6月時点)国内では乾癬に対して7種類の生物学的製剤が使われているが、どの薬剤も免疫原性や間質性肺炎などの副作用といった課題がある。小林氏は「今後は、乾癬だけでなく、希少疾患にも効果が期待できる新たな生物学的製剤の開発に期待したい」と締めくくった。

ヒュミラ発売10周年メディアセミナー